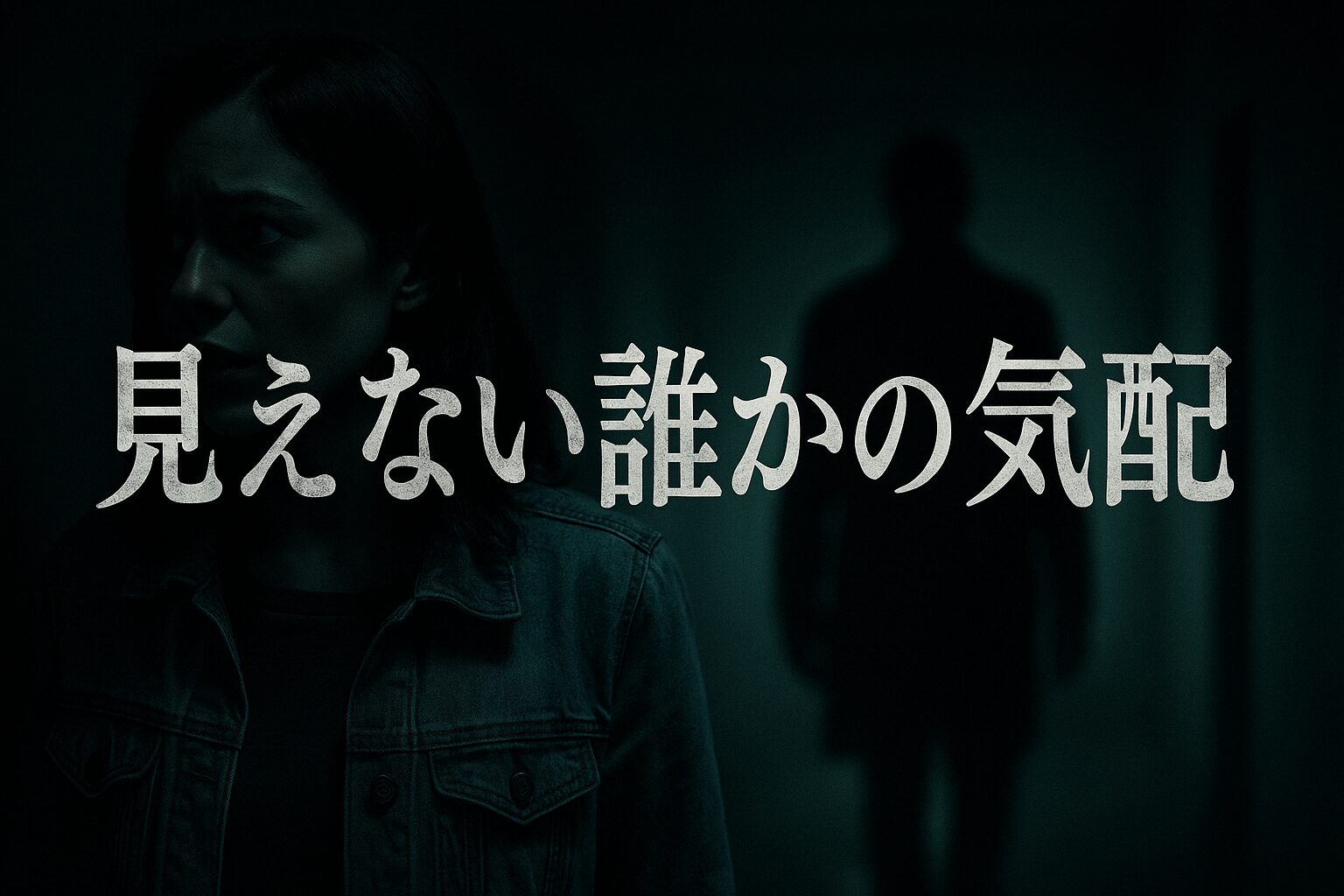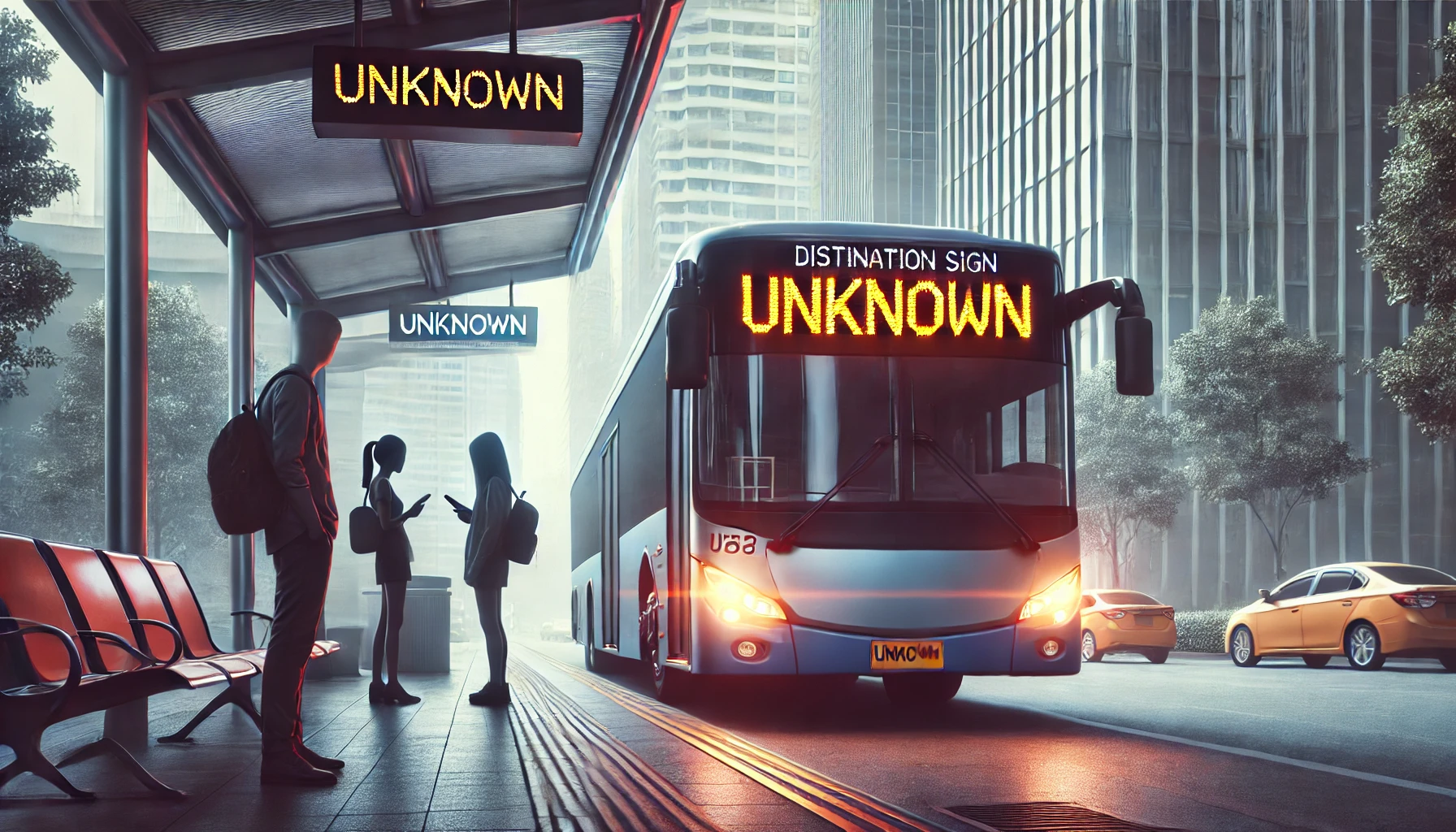夏の夜だけ開く「消える屋台」──お盆と狐の市に挟まれた異界経済学

はじめに

夏祭りの灯りが落ちかけた頃、ふと人波の隙間に現れる一軒の屋台。
地図にも記載はなく、商店会の人も「そんな店がありましたか?」と首をかしげます。
綿あめは雲のようにふわふわ、焼きそばは香ばしく、金魚すくいの水面には金色の光がちらつく──。
しかし翌朝、袋は空っぽ。
財布の中の500円玉は、なぜか庭先の落ち葉に変わっております。
「夢でも見たのだろう」と笑えるのは初回だけです。
二度目からは、背筋が少し冷えることでしょう。
もっとも、夏の暑さを考えれば、これは無料の冷房とも言えるかもしれませんが。
※本記事はエンターテインメント目的で制作されています。
江戸の怪談「燈無蕎麦」(あかりなしそば)

このような話は、実は江戸時代から存在します。
墨田区に伝わる本所七不思議の一つ「燈無蕎麦」はその代表例です。
夜更け、本所南割下水あたりに突如現れる蕎麦の屋台。
行灯に火が入らない、あるいは決して消えないという奇妙な現象が伴い、関わると災いが訪れるとされました。
浮世絵師・歌川国輝が描いた作例も残され、現地の親水公園にはレリーフまであります。
屋台と光の組み合わせは、江戸の人々にとっても格好の怪談素材だったようです。
翌日には“無かったこと”になる──狐・狸の葉札

民話では、翌朝になると品物の正体が失われる話が少なくありません。
特に有名なのが狐や狸の化かしです。
夜のうちは立派な小判や銀貨に見えても、朝にはただの木の葉や紙切れに変わってしまいます。
「葉札」や「木の葉小判」と呼ばれるこの現象は、全国各地に伝わっています。
宮城や関西の逸話では、酒や団子を葉札で買った狸が翌朝ばれて逃げた話や、宝玉から小判が出るもすべて落ち葉だったという話が残っています。
夜の経済圏では有効な通貨も、朝には無価値
──異界の為替レートは極めて変動的なのです。
なぜ夏祭りの夜なのか

夏祭りは単なる娯楽ではありません。
縁日が起源であり、もともと神仏と縁を結ぶ日でした。
江戸では参詣日に市が立ち、それが夜店へと発展しました。
信仰と娯楽が入り混じる場こそが、今の夏祭りなのです。
さらにお盆は、“あの世とこの世が交わる”とされる時期です。
迎え火・送り火、盆踊り
──いずれも境界線を曖昧にします。
そんな夜に現れる屋台は、まさにその狭間の存在と言えるでしょう。
世界にもある“異界市場”

日本独自かと思いきや、海外にも類似の伝承が存在します。
イギリスやアイルランドの妖精譚にはGoblin Market(ゴブリン・マーケット)が登場し、そこで買った品はすぐ腐る、食べれば二度と人間界に戻れないなどと語られます。
共通しているのは「見た目は豪華でも、価値は朝には消える」という点です。
価値基準が異なる経済圏では、きらびやかさも夜が明ければ霧散する
──まるでシンデレラの馬車がカボチャに戻るように、豪華さは夜明けとともに現実へと引き戻されるのです。
最後に

あなたの町の「消える屋台」は?
もし夏の夜、見慣れない屋台を見つけたら、立ち寄ってみるのも一興でしょう。
ただし翌朝、その戦利品が残っている保証はありません。
財布の中の硬貨が落ち葉に変わっていても、笑ってこう言えば良いのです。
「今年も異界側のレートは高かった」と。
さて、あなたの町にも“夜だけ現れる屋台”の噂はありませんか。
ぜひ調べてみて下さい。
次の夏、その屋台に出会えるかもしれませんよ。