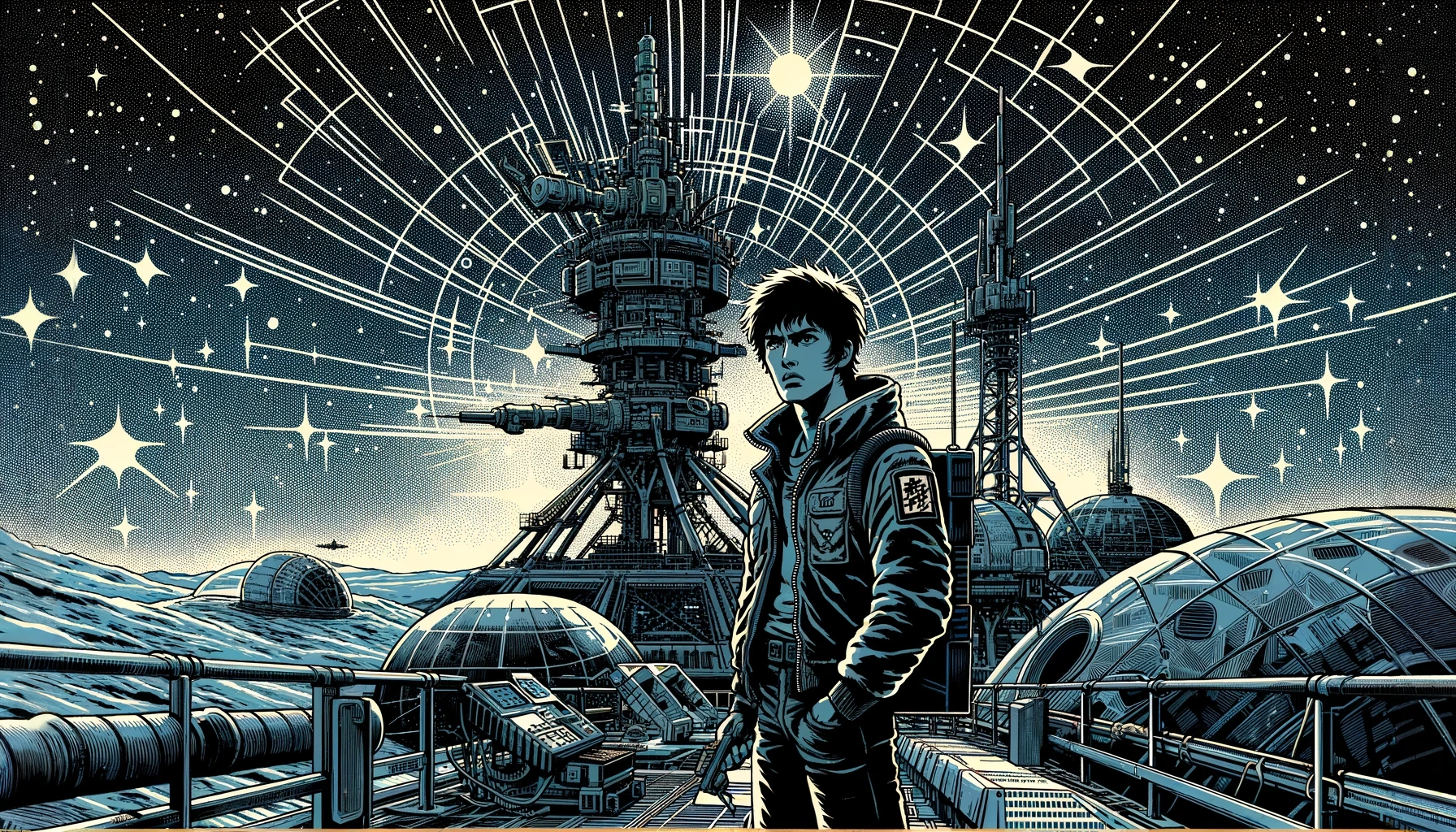挑戦の価値【ショートショート】
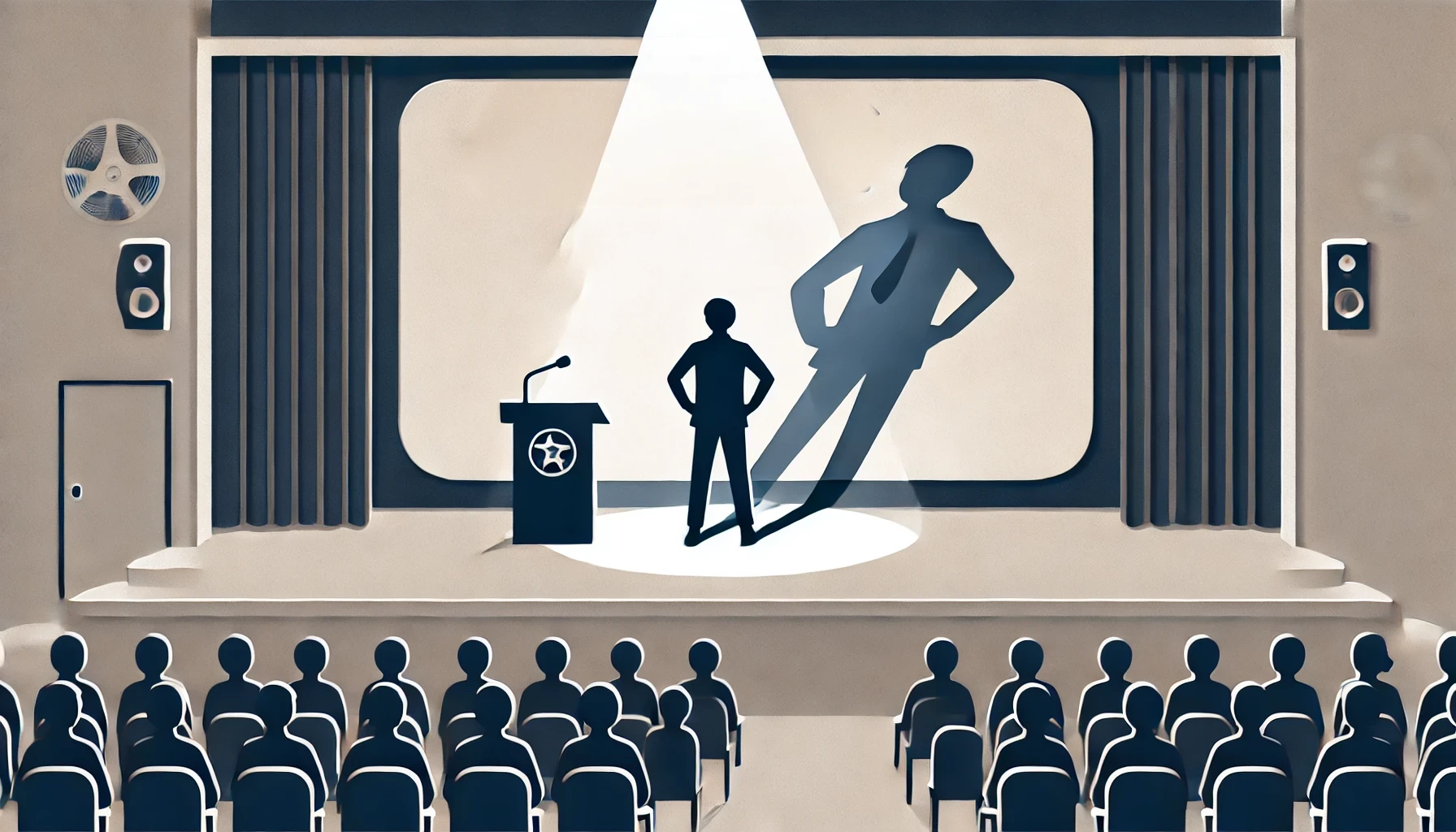
挑戦する勇気が、明日の自分を変える
セミナー会場は、参加者たちの熱気で満ちていた。
壇上の講師がマイクを手に取り、静かに問いかける。
「皆さん、成功のために必要なものは何だと思いますか?」
「自信!」と答える声が会場のあちこちから上がる。
講師は少し微笑み、静かに首を振る。
「それも大事です。しかし、それ以上に必要なものがあります」
彼は間を置いてから続けた。
「それは、セルフ・コンパッション――自分への思いやりです」
「セルフ・コンパッションとは何か?」
講師はスクリーンに映されたスライドを指さした。
- 自分の失敗を許すこと
- 自分を責めずに受け入れること
- 失敗から学ぶ勇気を持つこと
「例えば、仕事でミスをしたとします。そのとき、多くの人はこう考えます。『なんてダメなんだ』と。でも、セルフ・コンパッションを持つ人は違います。『ミスをしたけど、ここから学べる』と考えます」
最後列に座る一人の男性が手を挙げた。
「あの…それ、頭ではわかるんですけど、実際には難しいですよね」
講師は彼を見て微笑み、「確かに難しいです」と頷いた。
「でも、小さなことから始めてみてください。例えば、鏡を見てこう言うんです。『失敗しても、俺は価値がある』と」
男性は苦笑しながら呟いた
「それで変われるなら、世の中の人間はもっとみんな上手くやれてますね」
会場が笑いに包まれる中、彼は心の中で考えた。
(本当にそんなことで変われるのか…?)
セミナーが終わり、彼は帰り道の電車で窓に映る自分を見た。
窓ガラスには疲れ切った顔が映っている。
ふと、セミナー中の講師の言葉が頭をよぎる。
『挑戦することに価値がある』
彼は自分の過去の失敗を思い出した。
- 提案を却下された会議
- 上司に叱られたプロジェクトのミス
- 自分を責めて、何もできなくなった日のこと
「…また同じことを繰り返すのか?」
家に帰ると、スマホに通知が一件届いていた。
メッセージを開くと、同僚からの短い一文が目に飛び込んでくる。
『急だけど、明日のプレゼン頼む。準備時間なくてごめん』
彼は思わず声を出した。
「マジかよ…」
椅子に腰掛け、頭を抱える。
失敗の予感が頭をよぎった。
だが、ふとセミナーの講師の声が蘇る。
『まずは鏡の前で言ってみてください。失敗しても俺は俺だ、と』
男性は自宅の洗面所で鏡を見つめていた。
- 疲れ切った顔
- 乱れた髪
- シャツのシワ
彼は深呼吸し、小さな声で呟いた。
「失敗しても…俺は俺だ」
1回目、声が震えた。
5回目、少しだけ声が安定した。
10回目、彼は笑った。
「案外悪くないかもな」
翌日、彼は急遽、頼まれたプレゼンに挑んだ。
テーマは「自己成長」
資料は不十分、準備時間もない。
同僚は心配そうに尋ねた。
「大丈夫なのか?」
彼は小さく笑った。
「大丈夫。昨日、鏡の前で練習したから」
プレゼン会場。
緊張した面持ちの彼が壇上に立つ。
スポットライトが眩しい。
聴衆の視線が刺さるようだった。
彼は深呼吸をし、一歩前に出た。
「今日は、セルフ・コンパッションについて話します」
スクリーンに映るのは、シンプルな言葉だけだ。
『失敗しても、俺は俺だ』
少しざわつく会場を背に、彼は話し始める。
「僕はずっと、自分の失敗を責めていました。
会議で提案を却下されたり、上司に怒られたりするたびに、こう思っていたんです。『俺はダメな人間だ』と」
彼は一呼吸置いて、観客の反応をうかがう。
誰もが真剣に彼の言葉を聞いている。
「でも、昨日のセミナーで、鏡を見ながらこう言ってみたんです。
『失敗しても、俺は価値がある』と」
彼はスクリーンを指差した。
「最初はバカらしいと思いました。でも、10回繰り返してみると、どこか気持ちが軽くなったんです」
彼は少し笑いながら続けた。
「だからといって、突然完璧になるわけじゃありません。実際、今日のプレゼンも準備不足で、スライドも動かず、枚数だって足りません」
聴衆の間からクスリと笑いが漏れる。
彼は微笑みを浮かべた。
「でも、それでいいんです。大事なのは完璧であることじゃなくて、挑戦することだから」
彼は静かに手を胸に当てた。
「自分を許すことができれば、次の一歩を踏み出す勇気が湧いてきます。」
彼の言葉が静かに会場に染み渡る。
聴衆は一瞬の静寂の後、拍手を送り始めた。
次第にその拍手は会場全体に広がり、彼は少しだけ肩の力を抜いた。
(挑戦して良かった)
彼は心の中でそう呟いた。
プレゼン終了後、上司が彼を呼び出した。
「よくやった。ただし、次はもっと準備して挑め」
彼は深く頷いた。
「はい、次こそ完璧を目指します」
上司は軽く笑いながら続けた。
「実はな、この話を聞いていた取引先が、お前に講演を頼みたいと言ってきた」
「えっ…?」
「断る理由はないよな。お前の体験談はきっと、彼らの役に立つ」
彼は驚きのあまり一瞬固まったが、やがて小さく笑った。
「…そうですね。次はせめて、スライドがちゃんと動くようにしておきます」
上司は肩をすくめた。
「スライドなんて必要ないかもな。お前の言葉そのものが響くんだから」
オフィスを出て、夜風を感じながら歩き出す。
街灯に照らされる自分の影が、どこか少しだけ背筋を伸ばしているように見えた。
彼は空を見上げ、つぶやいた。
「失敗しても、俺は俺だ。でも、次はもう少しマシな俺になれそうだ」