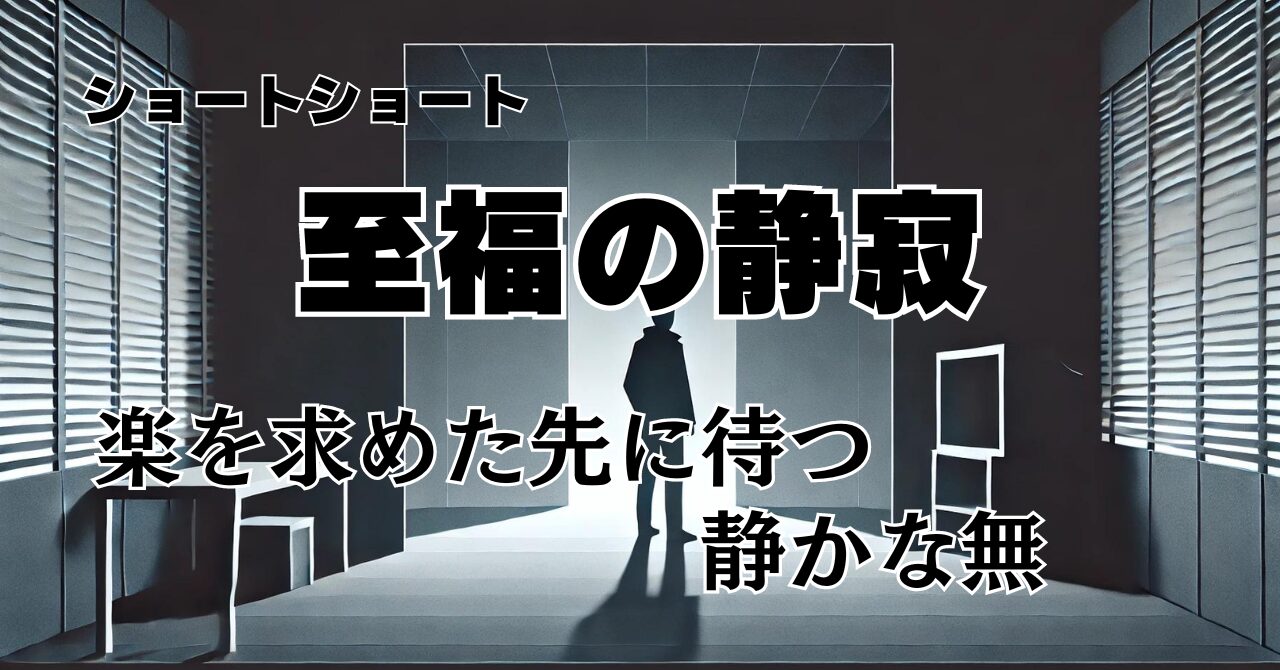自動化された夢【ショートショート】

感謝の言葉も、機械が代わりに
オオタは、いつものカフェで朝の時間を過ごしていた。
バターをトーストに塗り広げ、ジャムをその上に重ねる。
機械的に繰り返されるその動作に、彼はふと違和感を覚えた。
まるで自分が、ただの歯車の一部になってしまったような感覚だ。
窓の外では、人々が忙しそうに行き交い、車が同じリズムで流れていく。
だが、オオタにはそれがまるで遠くの出来事に思えた。
手元のコーヒーカップに指を滑らせ、その温もりを確認するが、すぐにその温かさも自分から遠ざかっていく。
会社への道すがら、いつもの電車に揺られながら、彼は何も感じなくなっていた。
耳に流れ込んでくるジャズの音すら、彼の心には届かない。
窓の外に映る景色は、まるで何度も再生されたビデオテープのように繰り返されているようだった。
オフィスに着くと、いつもと変わらない景色が広がっていた。
同僚たちは皆、無言で仕事を続けているが、その動きはどこか鈍く、重々しい。
「今日がその日だ」という無言の合図を、誰もが感じ取っている。
昼過ぎ、上司が全員を会議室に集めた。
彼は淡々とした口調で言った。
「新しい自動化システムが導入されることになりました。これからは、業務の大部分が機械で処理される予定です。皆さんの役割も縮小される見込みです。後で、個別に詳細をお話ししますが、すぐに変化が始まります」
その言葉が響いた瞬間、オオタは冷たい何かに包まれたような感覚に陥った。
予感はしていたが、それでも実際に聞くと体が硬直した。
誰も動かない、誰も声を出さない。
ただ、無機質な時間だけが部屋を支配していた。
夜、オオタは自宅に戻り、冷蔵庫からビールを取り出してソファに腰を下ろした。
缶の冷たさが彼の手にじわりと伝わる。
彼は一口飲んで目を閉じた。
昔、友人たちと一緒に夢を語り合った夜を思い出す。
だが、その夢は今ではどこにも存在しない。
テレビのニュースキャスターが、無感情に自動化の進展を報じていた。
「効率が劇的に向上し、新しい時代が始まります」と彼女は言う。
オオタはその声を聞きながら、空虚な気持ちに襲われた。
突然、インターホンが鳴った。
ドアを開けると、そこには配達ドローンが浮かんでいた。
無表情なドローンが「ありがとうございます」と告げ、機械的に荷物を差し出す。
それを受け取りながら、オオタはただ無言で見つめた。
「俺が感謝される側だったはずなのに…」
その思いが頭をよぎるが、彼は何も言わずドアを閉めた。
その音が、無機質な部屋に響く。
彼はしばらく缶を見つめた。
自分の手が冷たく、無機質な金属のように感じられる。
だが、すぐにその感覚は消えた。
これはただの錯覚だ、と思い直す。
だが、本当にそうだろうか?