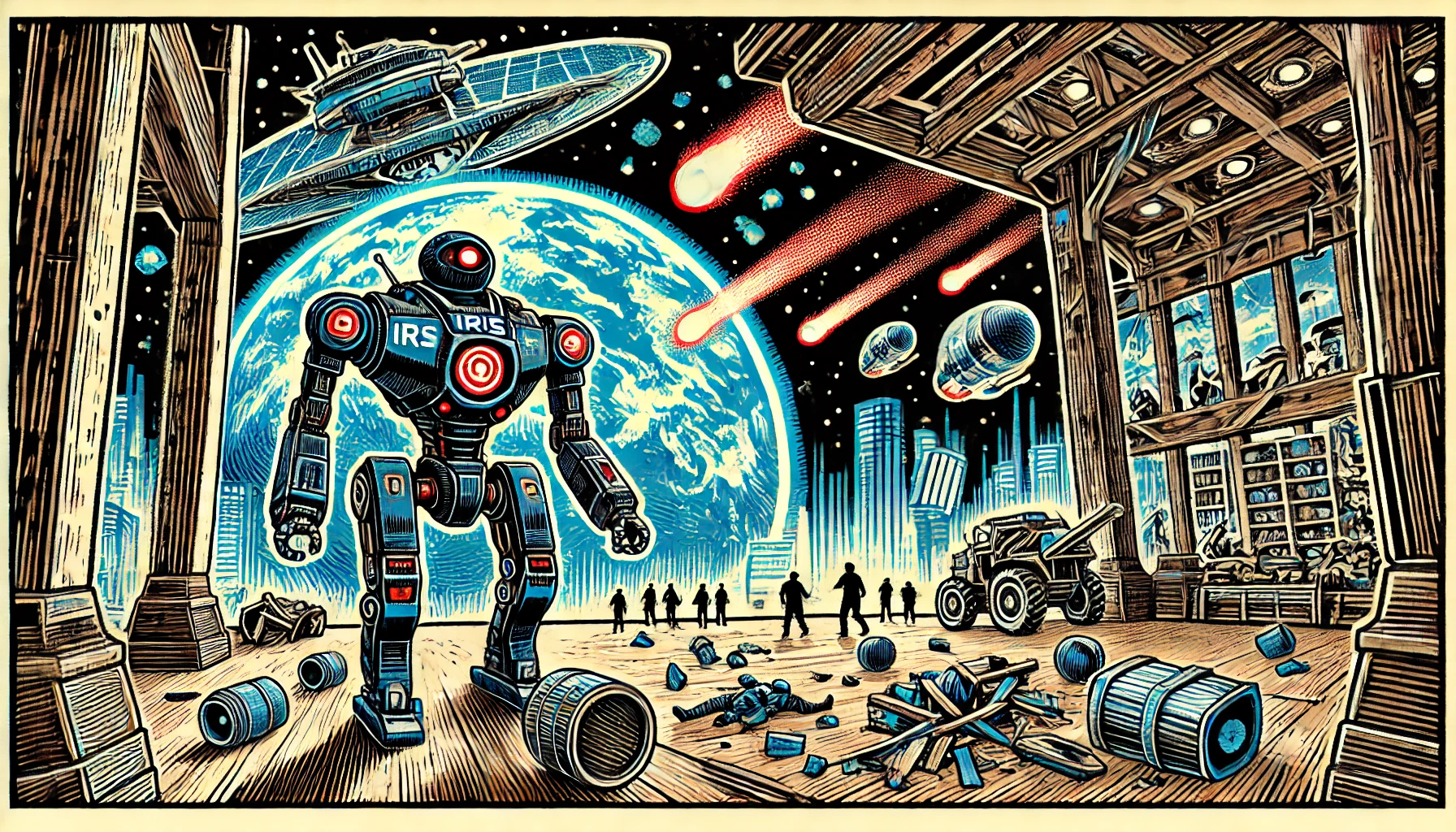シェア・オーバードーズ【ショートショート】

シェアの果てに、いつの間にか居場所がなくなった
カタオカはシェアリングエコノミーに心酔していた。
持たない暮らしが賢くて時代の先を行くと信じ、食器から家具、住まいまで何もかもシェアしていた。
友人たちが「シェア狂」と冗談を言おうとも、カタオカには信念があった。
「無駄を排して皆で共有することが、真に合理的な生き方だ」と。
しかし、その日、家に帰ったカタオカは奇妙な光景に出くわした。
リビングのソファに見知らぬ男が座っていたのだ。
男はテレビのリモコンを手に、平然と画面を見つめていた。
「誰だ?」
カタオカは眉をひそめ、声をかけた。
男は顔をゆっくりと向け、笑みを浮かべて答えた。
「シェアだよ。この部屋も俺のシェア対象なんだ」
一瞬、理解が追いつかなかったが、カタオカは無理に笑顔を作り「ああ、そうか」と頷いた。
だがその瞬間、胸の中に奇妙な感覚が芽生えた。
これはただのシェアなのか?
疑問はすぐに消し去ろうとしたが、その違和感はどこか心の片隅にしこりとして残った。
それから数日後、カタオカの部屋は急速に変わり始めた。
リビングには知らない顔が増え、冷蔵庫の中の食材が勝手に消えていく。
誰もが「シェアだ」と言い、まるでカタオカがいないかのように振る舞っていた。
そしてある夜、ベッドに横になろうとすると、見知らぬ男がすでにそこに横たわっていた。
「ここは…俺の寝床だぞ」
カタオカは声を震わせたが、男は目を開けてにやりと笑い、「まあ、シェアだからね」とあっさり言い放った。
その冷たい笑みと声が、カタオカの背筋に寒気を走らせた。
次第にカタオカは自分自身が誰であるのかも分からなくなりつつあった。
鏡を見たとき、自分だと思っていた顔は、どこかぼやけ、形が曖昧だった。
瞳の奥には自分の意志が見えず、まるで誰かの影が乗り移ったかのような、そんな気配が漂っていた。
さらに異常は加速した。カタオカが仕事から帰るたびに、家の中は異なる空間へと変貌を遂げていた。
見知らぬ家具、異質な配置、まるで「彼の家」ではなく、「他人の家」になっていく。
カタオカはその度に困惑し、周囲の住人たちに問いかけたが、誰もが彼を無視するかのように振る舞った。
「俺の家なのに、なぜ誰も俺を認識しないんだ?」
その問いは、誰に向けたものかすら分からなくなっていた。
そしてついに、カタオカは自分の名前を思い出すことすら難しくなった。
鏡を見て、そのぼやけた顔に「カタオカ」と呼びかけたが、その名はまるで無意味な音のように空虚に響くだけだった。
「俺は…誰だったんだ?」
彼は全てをシェアした結果、自分自身すら「シェアされ」、存在を失っていたのだ。
気が付けば、彼はただの空っぽな容れ物、他人に満たされて消え去った存在でしかなかった。