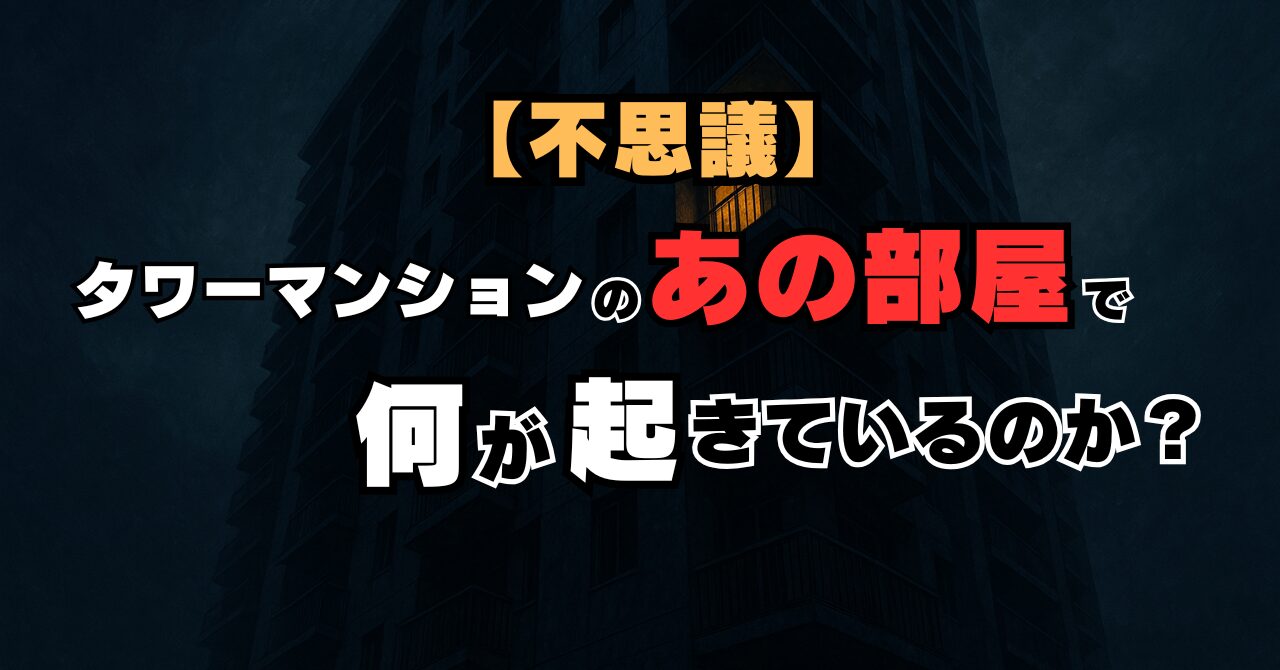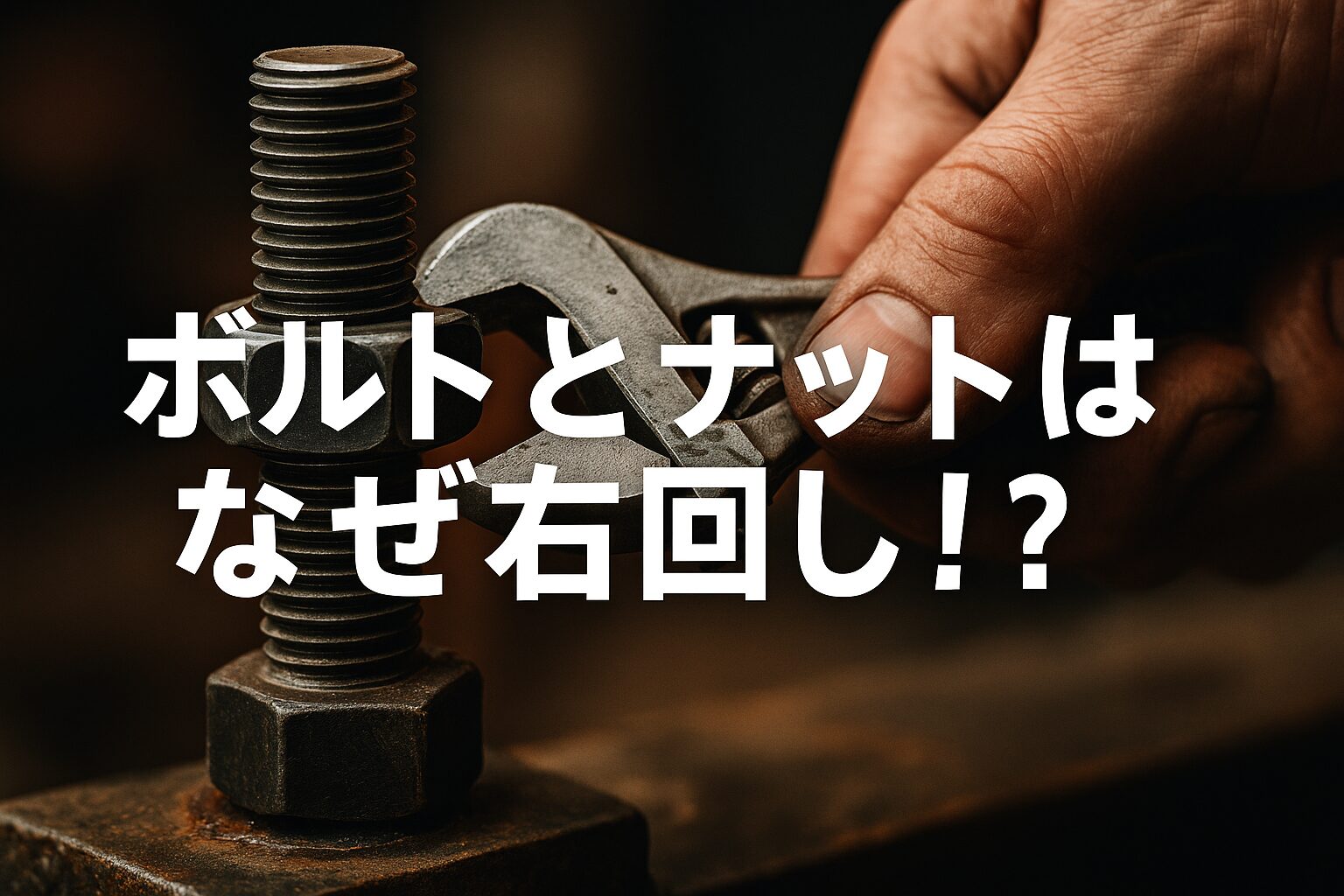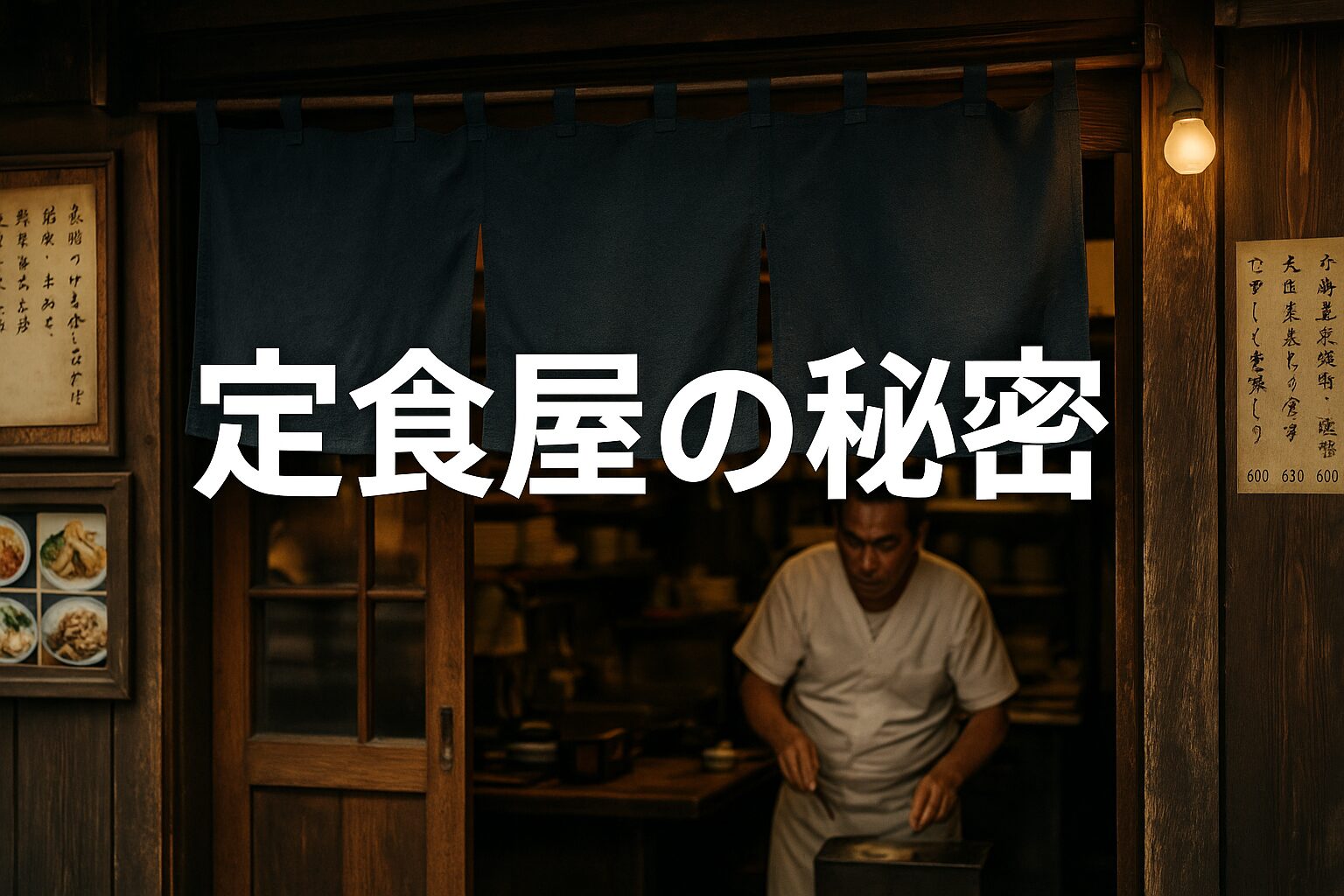街の八百屋はなぜ潰れないのか?——スーパーにない本当の強み

はじめに

コンビニは24時間光り輝き、スーパーは巨大な売り場で値引きシールが飛び交っています。
そんな時代に、商店街の一角で今も暖簾を掲げる八百屋があります。

子どもの頃から変わらない店主が、今日も「トマトが甘いですよ!」と声をかけてくれる――そんな光景が続いているのです。
なぜでしょう。
どうして街の八百屋は潰れないのでしょうか?

実はこれ、ただの“昔ながら”の風景ではありません。
八百屋には、スーパーやコンビニには真似できない生存戦略が隠されているのです。
※本記事はエンターテインメント目的で制作されています。
地域密着の魔力:顔なじみ経済

八百屋に足を踏み入れると、「今日はトマトが甘いですよ」や「この野菜は煮物にするとおいしいですよ」といった声が飛んできます。(現実にはあんまりこういう会話はしないかもですが……あくまで例題として……)
ちょっとした会話がきっかけで、気づけばリピーターになってしまう
――そんな力が八百屋にはあるのです。

顔なじみの関係は、まるで日常に組み込まれた“定期購買”のような役割を果たしています。
中小企業庁の調査によると、商店街は経営者の高齢化など課題を抱えつつも“地域の生活密着型”としての役割を維持しているといいます。

特に高齢者にとって、歩いて行けて、信頼できる人から買える八百屋は心強い存在です。
しかも「今日はこの大根安いですよ」といったリアルタイムな価格情報は、アプリのおすすめよりも人の温かさを感じられるのです。
スーパーにない“小回り力”

スーパーの野菜コーナーは整然と並び、規格外の曲がったキュウリなんてまず見かけません。
でも八百屋では「見た目は悪いけど味は最高」なキュウリを仕入れて、お手頃価格で並べます。
これが食品ロス削減にもつながっているのです。

さらに、御用聞きや配達、移動販売だって軽やかにこなすのが八百屋流です。
さらに、御用聞きや配達、移動販売だって軽やかにこなすのが八百屋流です。
大手チェーンがやろうとすればシステム導入や人件費で大規模な投資が必要ですが、八百屋なら「明日持っていきますよ!」で済みます。
言うなれば、“ご近所専属デリバリー”のような存在なのです。

最近は惣菜化や量り売りにも積極的です。
「人参は2本でいい」
「今日は少しだけカット野菜が欲しい」
といった声に応えられるのは、小さな規模ならではの強みです。
八百屋は、“ちょうどいい”を提供するプロなのです。

市場との強いつながり

「裏でどうやって仕入れているの?」と気になる方もいるでしょう。
答えはシンプルです。
青果流通の約6割は今も市場経由。
つまり、日本の野菜の大動脈は市場であり、八百屋はそこに直結しているのです。

市場で買参人(ばいさんにん)の資格を持てば、夜明け前のセリに参加し、新鮮で安い野菜を手に入れることができます。
仲卸(なかおろし)を通せば少量多品目で仕入れることも可能です。

その結果、店頭には「今日おすすめですよ!」と店主が胸を張る野菜が並びます。
要は、八百屋は情報戦でも勝っているのです。
潰れない理由は“時代に合わせた進化”

もちろん、すべての八百屋が生き残れるわけではありません。
統計的に小規模小売は減少傾向にあります。
しかし、残る店には共通点があります。

規格外品を価値ある商品に変えたり、SNSで情報を発信したり、データを使って仕入れを最適化したりと、“進化”しているのです。
たとえば、ある都市の小さな青果店は狭い売場ながら規格外品を活用し、粗利率を業界平均の2倍にまで高めました。

別の地域の八百屋はSNSを活用して多くのフォロワーを集め、アルバイトの採用までSNS経由で実現しています。
時代に合わせた八百屋は、もはや小売業というより“地域発スタートアップ”といえるかもしれません。
最後に

八百屋は街を支える“小さなエンジン”
「AIに仕事を奪われる」と叫ばれる時代に、八百屋は人間くさい声と笑顔で商売を続けています。

価格競争では大手に敵いませんが、“顔なじみ経済”“小回り力”“市場直結の仕入れ”という三本柱で、地域の暮らしに欠かせない存在になっているのです。
考えてみれば、八百屋はただの野菜屋ではありません。
ご近所SNSの前身であり、ローカル物流の担い手であり、食品ロス対策の実践者でもあります。
言うなれば、街を支える“小さなエンジン”のような存在だと言ってもいいでしょう。

次にあなたが八百屋でトマトを買うとき、その裏に隠された知恵とネットワークを思い出してみてください。
もしかすると、その一袋の野菜が、未来の商店街を支えているのかもしれません。