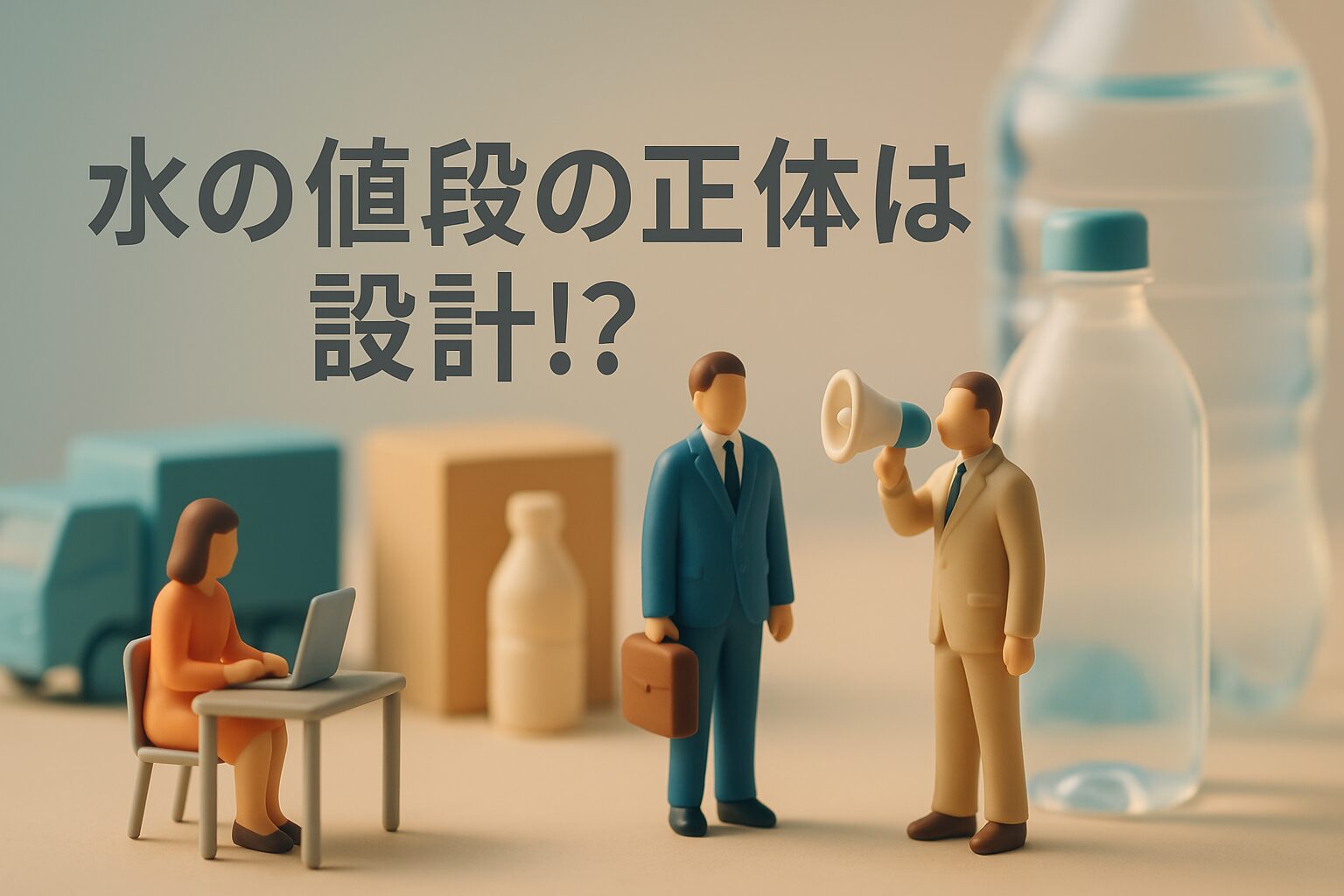町の電気屋はなぜ潰れないのか?——設置・修理、高齢者、顔なじみ、補助金まで“地域のインフラ”論

はじめに

量販店もネット通販も強いのに、なぜあの店は続いているのか?
大型家電量販店は圧倒的な品揃えと価格競争力がありますし、ネット通販はクリック一つで翌日配送。
……にもかかわらず、町の電気屋さんは今日も店を開け、着実にお客さんをつかんでいます。
しかも、地域によっては「混んでいてすぐには来てもらえない」という声すらあるほどです。

その理由はシンプルで、
「設置・修理という工事需要」
「高齢者顧客の課題」
「顔なじみの安心感」
「補助金やポイント制度の手続き代行」
という4つの柱に支えられているからです。

これらは地域に密着したインフラのような役割を果たし、大手と単純な価格勝負にならない仕組みを作っています。
この記事では、専門用語はできるだけ避け、身近な例を交えながら、町の電気屋さんがなぜ潰れないのかをわかりやすくご紹介していきます。
※本記事はエンターテインメント目的で制作されています。

1. 設置・修理という「工事需要」こそが強み

エアコンの取り付けは説明書を読めば誰でもできる?
実際はそう簡単ではありません。
壁に穴を開け、電源を分岐し、真空引きをして、室外機を設置して排水勾配まで調整する。ここまで聞いて「難しそう」と感じた方は正しいです。
実際、多くの作業は資格や経験が必要で、法律的にも無資格で行うことは禁止されています。

つまり、“誰でもできない=参入障壁が高い”のです。
だからこそ、機器をネットで購入しても、設置や修理は結局近所の電気屋さんに頼むという流れになります。
販売利益は薄くても、工事やメンテナンスでの収益が積み重なります。
季節の変化(夏のエアコン、冬の給湯器)や突然の故障によって、安定的に需要が発生するのです。

さらに修理や点検の経験は、信頼を積み重ねる投資でもあります。
「困ったときに助けてもらった」という体験は強く記憶に残り、次の買い替えやリフォームの際にも選ばれる理由となります。
比較サイトでは得られない関係性が、ここにあるのです。
2. リサイクルや撤去まで任せられる安心感

テレビ、エアコン、冷蔵庫、洗濯機。
新しく買うのは楽しいですが、古いものを処分するのは一気に難易度が上がります。
家電リサイクル法で定められた料金や手続きは複雑で、自治体や小売店ごとに違うルールがあったりもします。
初めての人には「これってどうやるの?」と戸惑うことが多いのです。

そこで活躍するのが町の電気屋さんです。
引き取りから申請までワンストップで対応してくれるため、お客さんは余計なストレスを抱える必要がありません。
さらに無許可回収によるトラブルもある中で、“顔が見える店”に依頼できる安心感はむしろ価値を増しています。

つまり、町の電気屋さんは「売って終わり」ではなく「最後まで責任を持つ」存在であり、この姿勢が支持されているのです。
3. 高齢者と顔なじみの関係が生む安心感

日本は急速な高齢化社会です。
新しい家電を購入しても、初期設定やWi-Fi接続、アプリの連携などでつまずく方は少なくありません。
そんなとき、配達から設置、設定、使い方の説明までサポートしてくれるのが町の電気屋さんです。

しかも「毎回同じ人が来てくれる」ことが大きな安心につながります。
高齢の親御さんにリモコンの操作で困りごとがあっても、顔なじみのスタッフに電話一本で解決。
これは取扱説明書よりも心強い存在といえるでしょう。

こうした細かな対応が信頼を積み重ね、やがてはリフォームや大型家電といった高額な取引にもつながります。
結果的に、地域の見守りや生活支援にも貢献しているのです。
4. 補助金やポイント制度を味方にする

省エネ家電や住宅リフォームには、国や自治体の補助金・ポイント制度が多く設けられています。
ただし、申請には専門的な知識が必要で、一般の人にとってはハードルが高いのが現実です。

ここで頼れるのが町の電気屋さんです。
「この制度を使えば自己負担はこれくらいです」と具体的に説明し、さらに見積もりから機器の選定、設置、リサイクル、申請までを一気通貫で対応してくれます。

これによってお客さんは損をせず、安心して買い替えを決断できます。
制度が毎年変わる中で、常に最新情報を把握し代行してくれる存在は、大手量販店やECには真似できない強みなのです。
5. 「買い物弱者」を支える地域インフラ

車を持たない、公共交通が少ない、インターネットが苦手。
そんな“買い物弱者”にとって、町の電気屋さんが配達や訪問をしてくれること自体が大きな価値になります。
ついでに消耗品を届けてもらえたり、生活の困りごとを気軽に相談できたり。
単なるお店以上の役割を果たしています。

これは商売であると同時に、地域の福祉にもつながっています。
量販店やECにはできない「最後の一歩」を埋める存在として、人口構造の変化とともにその重要性はますます高まっているのです。

6. 価格競争ではなく“関係資産”で勝つ

価格で勝てないなら、関係性で勝つ。
町の電気屋さんは定期点検や季節ごとの提案を通じて、お客さんとの関係を深めています。これはAIもネット通販も真似できない領域です。

さらに、保証延長や点検パック、消耗品交換などを「ゆるいサブスク」として提供すれば、収益は安定します。

中にはパン屋やカフェを併設して地域コミュニティを作る店も登場しています。
家電販売にとどまらず、暮らし全体をコーディネートする存在へと進化しているのです。
7. ビジネスに学べる“町の電気屋モデル”

町の電気屋さんのやり方は、実はあらゆるビジネスに通じます。
BtoBでもフリーランスでも、取り入れればファンが増える「生き残り戦略」が詰まっています。

- 納品して終わりではなく、その後の困りごとまで伴走する
- 顔が見える関係で、信頼を“積立貯金”のように増やす
- 制度や補助金を知恵として提供し、顧客の得につなげる
- 小さな御用聞きを積み重ね、大きな取引へ育てる

つまり「売って終わり」のビジネスから、「暮らしに溶け込む存在」になること。これこそが、町の電気屋さんが何十年も生き残り続ける秘密であり、現代のビジネスにも応用できる黄金ルールなのです。
最後に

町の電気屋は“生活のBGM”である
華やかな広告より、「この前は助かったよ」という一言。

最新テクノロジーより、壊れたときにすぐ駆けつけてくれる安心感。
ポイント還元より、補助金の申請まで面倒を見てくれる便利さ。
それらが積み重なり、町の電気屋さんは静かに強さを保っています。

エアコンの温度はリモコンで変えられますが、暮らしの温度を上げるのは人との関わりです。
シャッターが上がる音が、地域の生活のBGMである限り、この店はそう簡単にはなくならないのです。