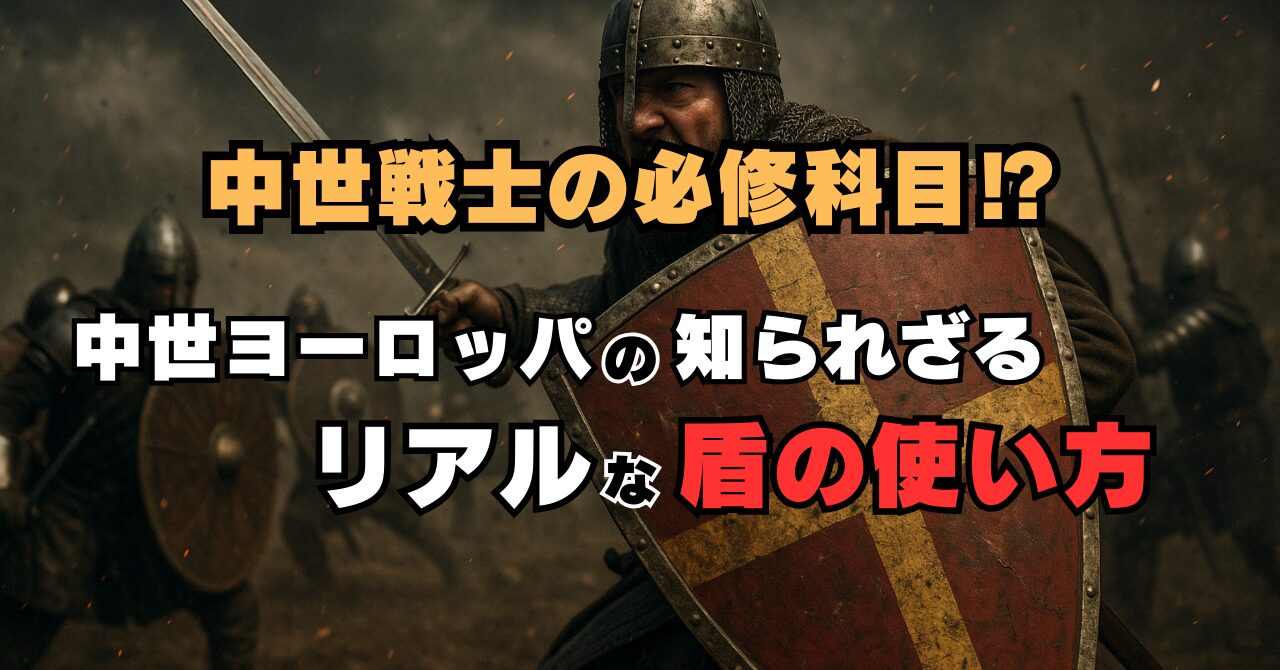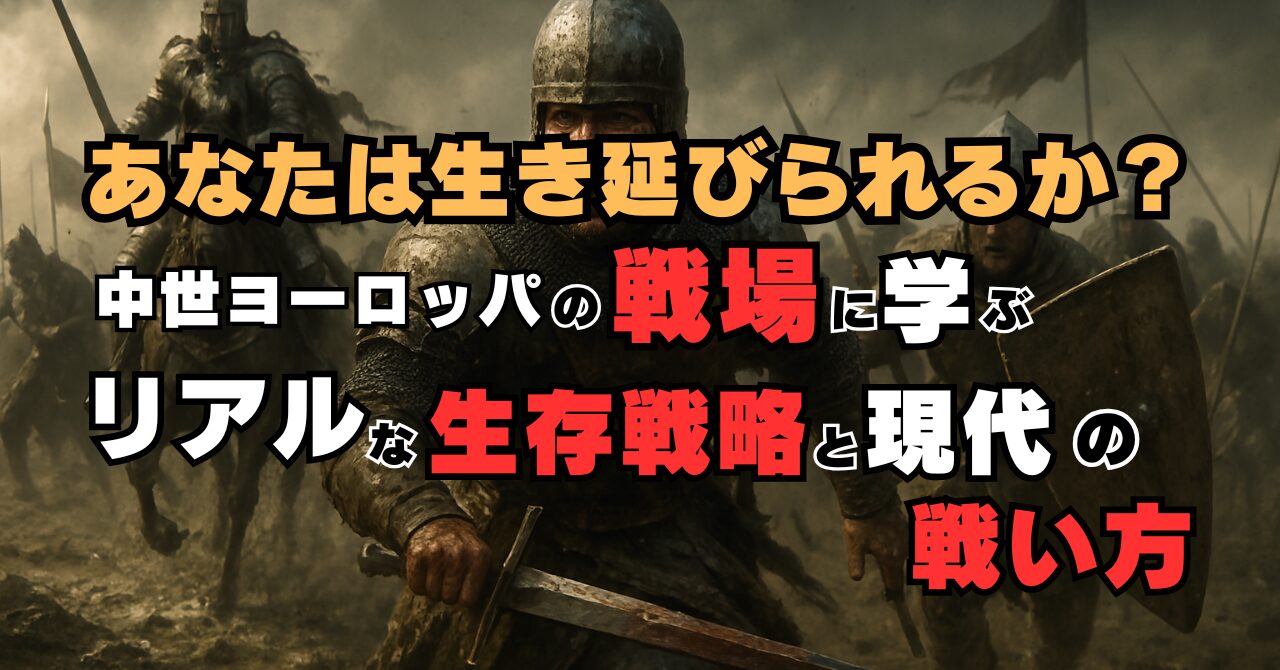なぜ彼らは逃げなかったのか──歩兵の“忠誠”と“洗脳”

はじめに

「逃げたら死刑、でも残っても死ぬ」ってどういうこと?
中世ヨーロッパの戦場と聞けば、つややかな鎧をまとった騎士や、堂々と馬にまたがる将軍の姿が浮かびます。
しかし、実際に泥と血の中で命を削っていたのは、名もなき歩兵たち。
彼らの多くは農民や町人で、武器は借り物、防具はボロ、報酬は雀の涙。
それでも「逃げない」
なぜか?
本記事では、その理由を心理と宗教から掘り下げます。
※本記事はエンターテインメント目的で制作されています。

1. 軍規という“鎖”

恐怖はあるが万能じゃない
14~15世紀のイングランド軍には、遠征ごとに「軍規(ordinances of war)」が発布されました。
無断離脱や隊列からの離脱、掠奪には死刑を含む厳罰が規定されていました。
とはいえ実務では赦免や減刑もあり、“即処刑”は必ずしも毎回ではありません。
つまり、恐怖は確かに存在するが、
それ一本で兵を縛ることはできなかったのです。
加えて1399年や1439年の法令では、一部の軍事犯罪は民事系統で裁かれるようになり、王権による乱用に一定の歯止めがかかっていました。
それでも兵士にとって「逃げる」という選択肢は、人生を一瞬で終わらせる博打でした。
2. 財布の力

危険と引き換えの“飴”
恐怖だけでは人は動かない。
動かすなら、飴も必要です。
百年戦争期の英軍では「インデンチャー(契約)」により日当が支払われました。
徒歩兵の相場は2ペンス、弓兵は3〜4ペンス。
現代でいえば「最低賃金ギリギリ」レベルですが、当時の農民にとっては現金収入自体が貴重でした。
さらに戦利品の分配や略奪の許可、捕虜をとれば身代金を得られるチャンスもありました。もちろんそれは命あっての話。
戦争は「命がけのギャンブル」でしたが、当たりを引けば一生分の稼ぎになる可能性もあったのです。
3. 仲間の目

羞恥と名誉が背中を押す
現代の軍事心理学でも指摘されるように、人は国家や大義のためというより「隣の仲間のため」に踏みとどまります。
中世の歩兵も同じ。
密集隊形の中で、横にいる仲間に背を向ければ、一瞬で「臆病者」の烙印を押されます。名誉は中世社会での生命線。
逃亡は社会的死を意味し、それは物理的死よりも恐れられました。
太鼓、旗、指揮官の叫び──
これらは単なる指示伝達ではなく、兵の一体感を維持する“心理的糊(のり)”でもありました。
スイス槍兵(15〜16世紀にヨーロッパ各地で傭兵として名を馳せた、長槍を密集陣形で操るスイス出身の歩兵部隊)のように、「逃げれば共同体の面子が潰れる」という社会的圧力が、兵を列に釘付けにしたのです。
4. 祈りと赦し

宗教が恐怖を上書きする
戦場には司祭が帯同し、戦闘前には祈祷やミサが行われました。
1415年のアジャンクールの戦いでも、英軍は司祭団の祈りで戦いに臨みました。
死は恐怖ではなく「神のもとへ行く道」と意味づけられ、兵士は安心感すら覚えたといいます。
十字軍時代には、教皇ウルバヌス2世が「異教徒と戦い、道中で死ねば罪はすべて赦される」と宣言。
死は敗北ではなく、永遠の報酬への切符となりました。
聖なる旗や遺物は「神が味方している」という心理的防壁を強化しました。
5. コミュニティの圧力

逃げると村ごと罰
中世イングランドでは、アームズ制(国民に武器の所持と整備を義務づける制度)やウィンチェスター法(1285年制定の治安・防衛法で、地域ごとに武器や兵士を準備させる規定)が、戦時動員の法的基盤となっていました。
これらの法律は「武器を持てる=戦時には出動せよ」という義務を明文化し、各村や郡は国王や領主の命令に応じて兵を供出しなければならなかったのです。
逃げれば村全体が罰せられ、家名が汚されます。
兵士の行動は個人の問題ではなく、共同体全体の運命を左右しました。
逃げることは、自分だけでなく家族や隣人を危険にさらす行為だったのです。
6. 補給と食事

我慢と戦略の間で
兵士の食料は、補給隊、現地調達、略奪の組み合わせで確保されました。
硬く乾燥したパン(ハードタック)は長期保存と輸送に適し、味は二の次。
保存性重視の食事は、兵士にとっては忍耐の訓練であり、同時に戦略的選択でもありました。
補給が途絶えれば、士気は急落。
逆に満腹の兵は「あと一戦やってもいいか」と思える。
胃袋は戦争のもう一つの戦場だったのです。
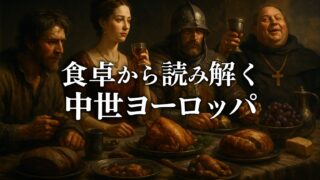
事例:アジャンクールとスイス槍兵

アジャンクール(1415年)では、英軍は数で劣りながらも、戦闘前に司祭たちが行った祈りによって「自分たちは神に見守られている」という強い精神的支えを得ていました。
この宗教的高揚は恐怖心を和らげ、兵士に落ち着きと目的意識を与えたのです。
その信念と隊列維持によって、英軍はフランス軍の突撃をしのぎ、勝利を収めました。
スイス槍兵は15〜16世紀にかけてヨーロッパ各地で恐れられた精鋭傭兵部隊で、長槍を装備し、深く密集した隊形で敵に突進する戦法を得意としました。
特にブルゴーニュ戦争やイタリア戦争などで、重装備の騎士を正面から撃退し、歩兵でも騎兵を打ち破れることを証明しました。
その戦いぶりは同時代の戦術思想に衝撃を与え、各国軍に模倣されるほどでした。
どちらも、恐怖と不利を「規律・名誉・宗教・仲間意識」で相殺した、象徴的な事例です。
最後に

“忠誠”と“洗脳”のグラデーション
歩兵たちは、
必ずしも王や領主への純粋な忠誠だけで動いたわけではありません。
恐怖、金、仲間、宗教、共同体の圧力
──それらが複雑に絡み合い、「逃げられない」状況を作り出していました。
それは一種の洗脳でもあり、生存戦略でもありました。
勇気と恐怖、誇りと強制、その境界はあいまいです。
名もなき兵士たちの足跡は、歴史の中でほとんど語られません。
しかし、国境や王国を守ったのは、彼らの一歩一歩でした。
英雄とは、名を知られる者だけではないのです。
「彼らが残したものは、勝利の記録よりも、仲間と共に戦った事実そのものだったのかもしれません」

4コマ漫画「逃げられない理由」