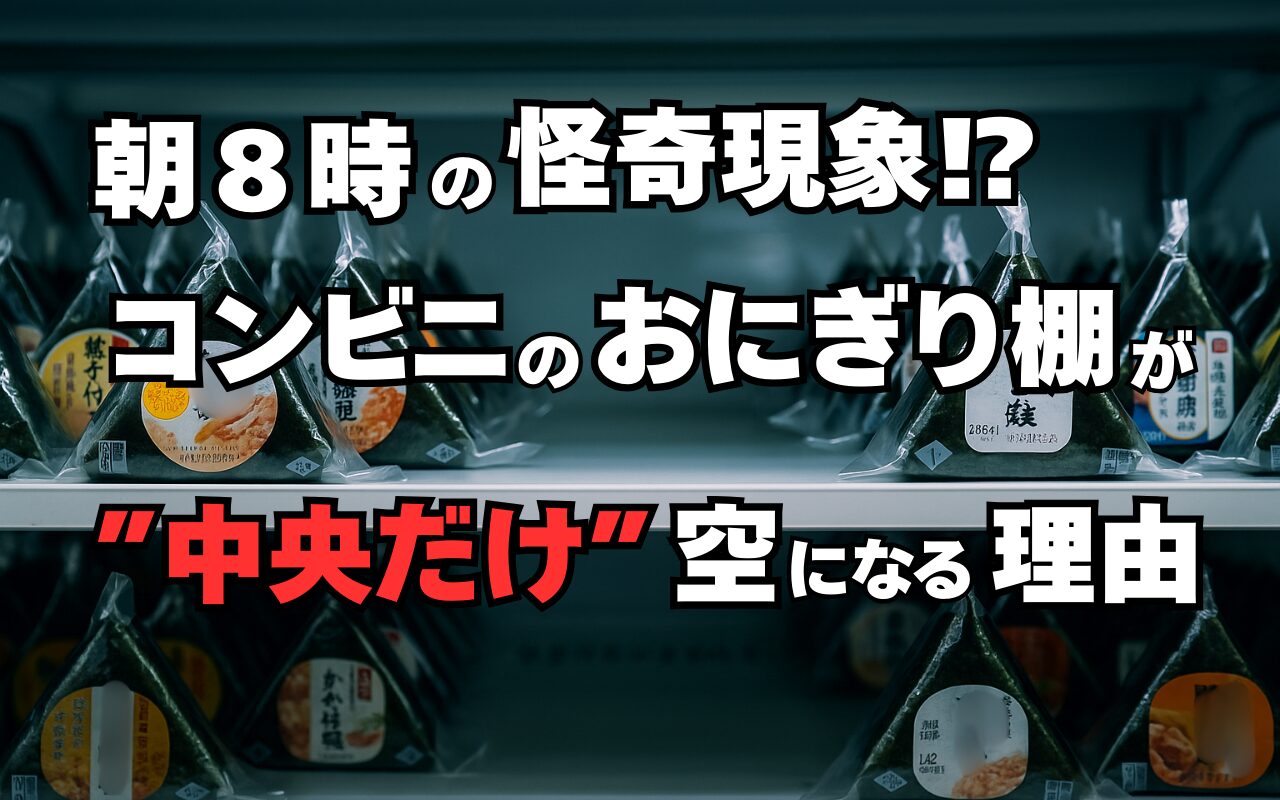水にも国民性ってあるんですか?─―“好きな水”で読む世界カルチャー

はじめに

1杯の水から、世界がちょっとだけ見えてくる
海外旅行に行くと、まずコンビニ(っぽい店)でやること。
それは――その国のミネラルウォーターを1本買うことです。
ラベルを見てみると、聞いたことのある名前がずらり。
「お、エビアンだ」
「サンペレグリノもある」
「なんかドイツっぽい名前の炭酸水もあるぞ…読めないけど」
一方、日本に戻ると、
「南アルプスの天然水」
「い・ろ・は・す」
「ウィルキンソン」
などおなじみの顔ぶれ。

同じ「水」なのに、国によって好まれる水がまったく違う。
硬水・軟水の違いだけじゃなくて、その裏には地質・歴史・食文化・ブランド神話まで、いろんな物語が詰まっています。
というわけで今回は、
「世界のミネラルウォーター文化:なぜ国によって好きな水が違うのか?」
をテーマに、ちょっとした“飲めるカルチャー記事”をお届けします。
コーヒー片手でもいいですが、せっかくなのでお好きな水を1杯、用意して読んでみてください。
……あ、読了後に「今日の水うまっ」と思ってもらえたら嬉しく思います。
※本記事は筆者個人の感想をもとにエンターテインメント目的で制作されています。
硬水・軟水って、結局なにが違うの?

まずはサクッと基本だけ。
水の“硬さ”を決めているのは、主にカルシウムとマグネシウム。
この2つが多いほど「硬水」、少ないほど「軟水」です。
ざっくりイメージで言うと、
- 硬度 0〜60 mg/L … 軟水(さらっと淡麗)
- 60〜120 mg/L … ちょい硬め
- 120 mg/L以上 … しっかり硬水(ミネラル感あり)
くらいで考えておけばOK。
日本の水道水は全国平均で約50 mg/L前後。
つまり、ほぼ全土が「軟水ゾーン」にいます。
一方、ヨーロッパの多くの地域では、
硬度150、200、場所によっては300 mg/L以上なんていうガチ硬水も珍しくありません。
「そりゃ味の感じ方も変わるわ…」というレベルで、
私たちが普段飲んでいる水とはベースのキャラクターが違うわけです。
日本が「軟水王国」なワケ

■せっかちな雨と火山列島
日本の水が軟水寄りなのは、性格が穏やかだから……ではなく、地形と地質のせいです。
ざっくり言うと、
- 山が急で、川も短い
- 雨が降ってから海に流れ出るまでの時間が短い
- その間に岩からミネラルを溶かし込む暇があまりない
という「せっかちルート」を通っているため、
水にカルシウムやマグネシウムが溶け込む量が少なくなります。
しかも日本の山は、
カルシウムをあまり出さない火山岩や花崗岩が多い。
石灰岩のように「ガンガン溶けてミネラルどうぞ!」というタイプではないので、
結果として全体的にやさしい軟水になりがち、というわけです。
例としてよく挙げられるのが「サントリー 南アルプスの天然水」
水源の白州の地下水は花崗岩由来で、硬度は約30 mg/L。
教科書レベルの軟水です。
つまり、
急な山から短い距離で海に流れ出る“せっかちな雨”と、
火山岩・花崗岩という「控えめな岩」が組み合わさった結果、
日本は“軟水王国”になった。
というストーリーになります。
ヨーロッパは「石灰岩の大陸」

■ゆっくり旅する“ミネラル濃いめの水”
一方、ヨーロッパの大地は石灰岩・チョーク・ドロマイトといった、
カルシウムたっぷりの堆積岩が広く分布しています。
イメージとしては、
- 山から海までの傾斜がなだらか
- 地中の石灰層の中を、水がのんびり時間をかけて旅する
- その間にカルシウム&マグネシウムがたっぷり溶け込む
という「スローライフな水の旅」
この結果、
ドイツ、イタリア、フランス、イギリス南部などには、
硬度150〜300 mg/L以上の「しっかり硬水」エリアがゴロゴロ存在します。
ヨーロッパの水は、
「石灰岩の大地を長い時間かけて旅してくるうちに、
カルシウムとマグネシウムをリュックいっぱいに詰め込んだ水」
だと思うと、少し可愛く感じないでしょうか。
和食は“水の料理”だった

■軟水がつくる出汁とお茶
では、この違いが生活や味覚にどう関わってくるのか。
日本で大きいのはやはり和食×軟水のコンビです。
軟水は、
- 昆布のグルタミン酸
- かつお節のイノシン酸
といったうま味成分を引き出しやすいと言われています。
この2つが合わさると、うま味は7〜8倍に感じられるとも。
透明感のある出汁、ふっくらした白米、
香り高い緑茶や抹茶──どれも軟水あってこそ。
だから日本の料理研究家や板前さんの中には、
「海外でもわざわざ日本の水を持ち込む」人もいるほどです。
和食は“素材の味を引き出す料理”であり、
もっと言えば“水の料理”でもある。
こう考えると、日本人が無意識のうちに
- 「柔らかい水=おいしい」
- 「無味無臭に近い水が好き」
となるのも、納得がいきます。
ヨーロッパの硬水が育てた、パン・チーズ・肉料理

硬水の強みは、がっつり系の料理と相性がいいところ。
たとえば、
- 肉を煮込むとき、硬水中のカルシウムがタンパク質と反応して、
アクを出しやすくしてくれる - ビーフシチューやポトフのような煮込み料理に、
コクと深みが出やすい - パスタを硬水で茹でると、コシが出てアルデンテに仕上がりやすい
などなど。
パンやチーズ、ソーセージ、肉料理が主役のヨーロッパでは、
「硬水 × 肉 × パン × チーズ」
という組み合わせが、食卓の標準装備として長い時間をかけて定着していったわけです。
脂っこい料理には、
ミネラル感のある炭酸水を合わせて口の中をリセットする、という楽しみ方も定番。
「ワインの前に、とりあえずペリエで喉を準備する」なんていうのは、
ちょっと通ぶりたい夜に真似したくなる儀式です。
そもそもミネラルウォーターって“薬”だった

突然ですが質問です。
ミネラルウォーターの始まり=オシャレな飲み物だと思ってましたか?
実は……。
最初は完全に治療薬ポジションでした。
舞台はヨーロッパ。
16世紀ごろ、ベルギーのスパ(Spa)やフランスのヴィシー、ドイツのアポリナリスなど、湧き水の名所でこう囁かれます。
「この水、飲むと体にいいらしいぞ」
現代ならSNSでバズって即完売です。
当時はSNSがないので、人々は徒歩でバズを追いかけるスタイル。
何日も旅をして、ただ“水を飲む”ために温泉地へ向かいました。
これぞストイックなデトックス旅。
しかも当時の感覚は、
「湧き水を飲む=治療行為」
いま風に言えば、ウェルネス(心身の健康を整える生活習慣)ですね。
ヨガも腸活も無い時代、彼らの健康法は“水を飲む”でした。
シンプルすぎる。

ところが療養者が増えすぎて、問題が発生します。
A「飲みたいけど遠くて行けない!」
B「医師が処方したいのに(水が手元に無くて)患者が来ない!」
そこで生まれたのが、まさかの解決策。
湧き水を瓶に詰めて持ち帰ろう!
(発想は現代のテイクアウトと変わらない)
こうして薬局で売られる“ボトル入りの水”が誕生しました。
つまりミネラルウォーターの原点は、ライフスタイル飲料ではなく、
ほぼ“飲む薬”だった。
そして時代が進むと、その特別な水はこう変身します。
「治療の水」 → 「ブランドの水」 → 「おしゃれアイテム」
健康のために飲まれていた湧き水は、
気づけばセレブのカバンに入り、雑誌の撮影小物になり、
インスタで「#evian」のタグとともに投稿される存在に。
水なのに薬→ブランド→ファッション小物へ進化。
どの界隈のタレントより出世してる。
水、最初からわりとラグジュアリー。
世界の有名ブランド、その“生まれたときの話”

エビアン:貴族を救った「奇跡の水」

フランス・アルプスのふもと、エヴィアン=レ=バンでのこと。
1789年、体調を崩したフランス貴族が、
散歩の途中に出会った湧き水を飲み続けたところ、
症状が改善した――というのが、エビアン神話のスタートです。
その水源「カシャ水源」は、のちに温泉施設として整備され、
さらに1826年にはボトリング工場ができ、本格的なミネラルウォーターとして販売が始まります。
いまやエビアンは、
ファッションスナップやセレブの手元によく写り込む「ライフスタイル・アイコン」
貴族の不調を救った湧き水が、
200年後にインスタの小道具になる。
歴史の捻じれ方、ちょっとおもしろいですよね。
ペリエ:炭酸水界の“シャンパン”を目指したフランス炭酸

南フランスのヴェルジェーズで湧く、天然の炭酸泉。
この水はローマ時代から知られていましたが、
ブランドとして動き出したのは19世紀。
医師ルイ・ペリエが源泉を買い取り、
スパとボトリング事業をスタートさせます。
のちにイギリス人実業家ハームスワースが資本参加し、
「シャンパンのようなエレガントな炭酸水」としてイギリス市場で大ヒット。
特徴的な緑のボトルは、
もともと「シャンパンボトルを参考にした」とも言われています。
ペリエは、炭酸水というより“気取った水”。(※あくまで個人の感想です)
レストランで頼むとき、
ちょっと背筋が伸びるのは、きっとボトルのせいです。
サンペレグリノ:温泉保養地がテーブルの上へ

イタリア北部、アルプスのふもとサン・ペレグリノ・テルメ。
中世から知られる鉱泉で、
「レオナルド・ダ・ヴィンチがこの水を調査した」という伝承まであります。
13世紀ごろから貴族たちが療養に訪れ、
19世紀には本格的な分析・ボトリングが進み、
1899年に「サンペレグリノ温泉株式会社」が設立。
赤い星と青いラベルのボトルは、
いまや世界中のイタリアンレストランの定番です。
もともとは“山奥の療養地の水”が、
いまや“都会のテーブルのマストアイテム”。
“療養地の湧き水”から“食卓のスター”へ
――人生(いや水生?)何が起きるかわかりません。
ゲロルシュタイナー:火山と石灰岩が出会った“天然ソーダ”

ドイツ西部の火山アイフェル地方からやってくるのが、ゲロルシュタイナー。
火山由来の二酸化炭素と、カルシウム・マグネシウムを含む岩石が組み合わさり、
ミネラルたっぷりの天然炭酸水になります。
総ミネラル量は2000 mg/L超。
数字だけ見ると「え、しょっぱくない…?」と思いますが、
味は意外とバランスがよく、「塩辛くも苦くもない中庸の味」とメーカーは説明しています。
「ちゃんと硬いのに、意外と飲みやすい」
――ドイツ人っぽい性格の水、と言ったら怒られるでしょうか💦
ボルヴィック:火山がもたらした、“巨大フィルター”

フランス中部、オーヴェルニュ地方の火山地帯。
ここで13,500年前に起きた火山活動によってできた溶岩や火山岩の層を、
雨水が約5年かけてゆっくり浸透していきます。
その自然ろ過システムを通って湧き出すのが、ボルヴィック。
ブランドとしてのボトリングは20世紀に入ってからですが、
「太古の火山が現代のミネラルウォーターブランドを育てた」と聞くと、
一杯の水のバックグラウンドが急にスケールアップします。
日本のブランドにも、ちゃんと物語がある

海外ブランドに目が行きがちですが、日本勢にも面白いストーリーが隠れています。
ウィルキンソン:英国人の“寄り道”から始まった炭酸水

明治時代、イギリス人のジョン・クリフォード・ウィルキンソンが神戸に滞在していたときのこと。
1889年、宝塚近郊で狩りをしている最中に、
偶然、自然の炭酸泉を発見します。
そこから炭酸水の事業を始め、
のちに日本企業に引き継がれ、
いまや「強炭酸と言えばウィルキンソン」の地位を獲得。
日本有数の老舗炭酸ブランドの起源が、
「イギリス人ハンターの寄り道」だったというのが、なんとも良いオチです。
サントリー天然水:『水と空気はタダ』への挑戦

1991年に発売された「サントリー 南アルプスの天然水」
いまではコンビニの主役級ですが、当時はかなり大胆なチャレンジでした。
昭和の感覚では、
「え、水を“買う”の?」
「水と空気はタダでしょ?」
という声が多数派。
ところがサントリーは、
- 日本各地の名水を厳選してボトル化
- 水源保護や森づくりとセットでブランド化
- 「南アルプスの自然=このボトルの価値」という物語を丁寧に伝える
ことで、「水をお金を出して買う文化」をじわじわ日本に根付かせていきました。
いまや日本人1人あたりのボトル水消費量は、年間約26L。
ヨーロッパ諸国(100〜170L)と比べるとまだ少ないですが、
「水を買うなんて…」と言われていた時代から考えれば、かなりの変化です。
結局、人は“慣れた水”をおいしいと思う

ここまでいろいろ語ってきましたが、
結局のところ、人間の舌はとても保守的です。
- 日本人:子どものころから軟水で育つ
→ 「さらっとしてる水=おいしい」と感じがち - ヨーロッパの多くの人:硬水で育つ
→ 軟水を「なんか物足りない」「味がしない」と感じることも
つまり、
「どの水が一番おいしいか?」ではなく、
「どの水で育ってきたか?」
の違いが、好みを大きく左右しているわけです。
恋人の好み、コーヒーの濃さ、カップラーメンのお湯の量――
なんでも「自分のデフォルト」がいちばん落ち着くのと同じですね。
最後に

今日の一杯に、物語をひとつ足してみる
冷蔵庫を開けると、
透明なペットボトルが何本か入っている。
それは単なる「水分補給アイテム」かもしれませんが、
視点を少し変えると、そこにはいろんな物語が隠れています。
- せっかちな雨が山を駆け下りてつくった、日本の軟水
- 石灰岩の大地をのんびり旅してきた、ヨーロッパの硬水
- 貴族の不調を救った湧き水
- 山奥の温泉保養地から世界のテーブルへ旅した炭酸水
- 英国人の寄り道から始まった日本の炭酸ブランド
どれも、ラベルの裏側にひっそり書いてありそうで、
でも実際には書いていない物語たちです。

次にコンビニで水を選ぶとき、
もし少しだけ時間があれば、いつもの一本の隣に「背景の違う一本」を並べてみてください。
エビアンと南アルプス。
サンペレグリノとウィルキンソン。
ボルヴィックとい・ろ・は・す。
国によって好きな水が違う、
その理由を知ってしまった私たちは、
きっと少しだけ“世界に詳しい喉”になっているはずです。
そしてそのとき、
ボトルのキャップを開けるカチッという音が、
少しだけ、物語の扉が開く音に聞こえたら――
今日の一杯は、きっといつもよりおいしい……といいな。