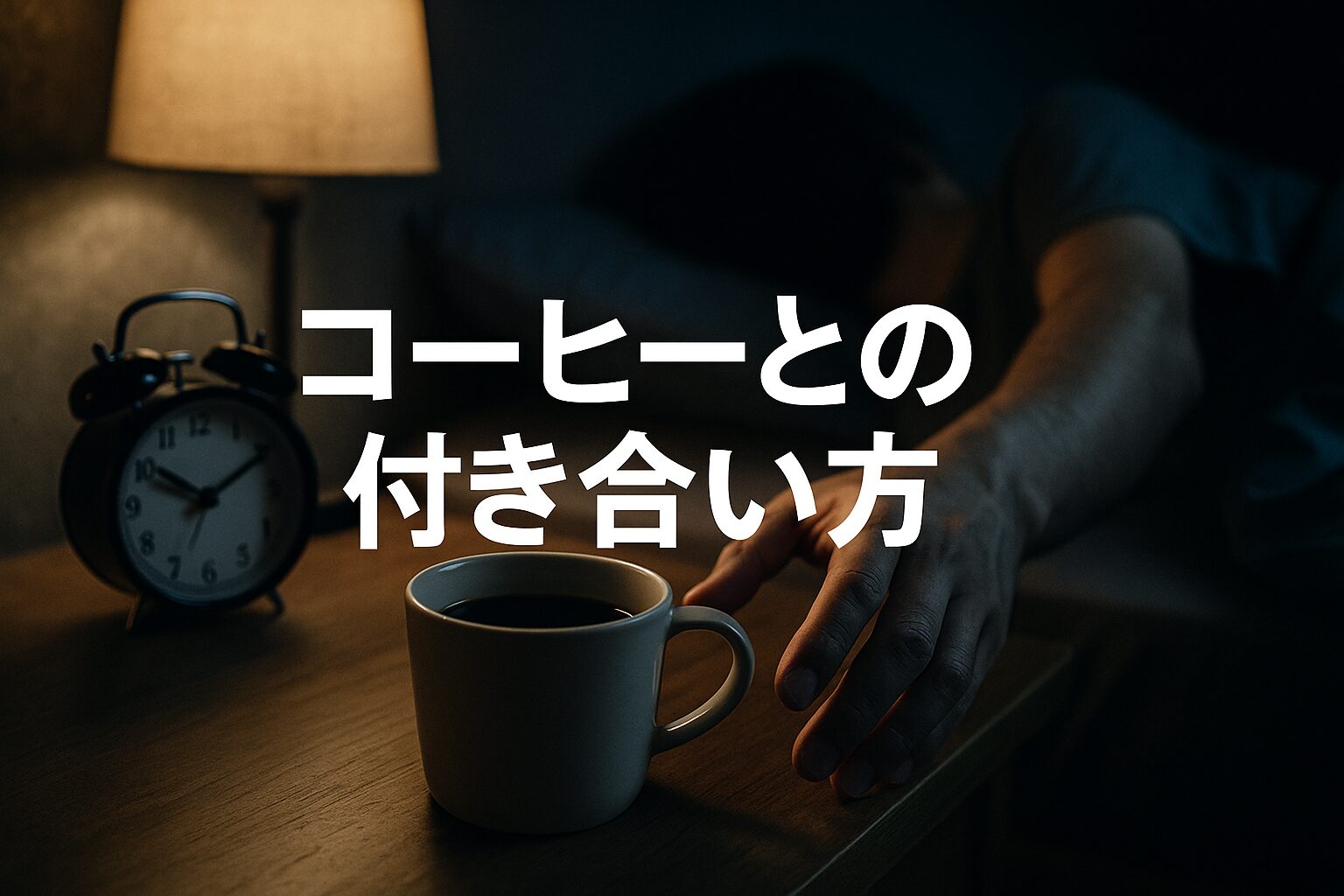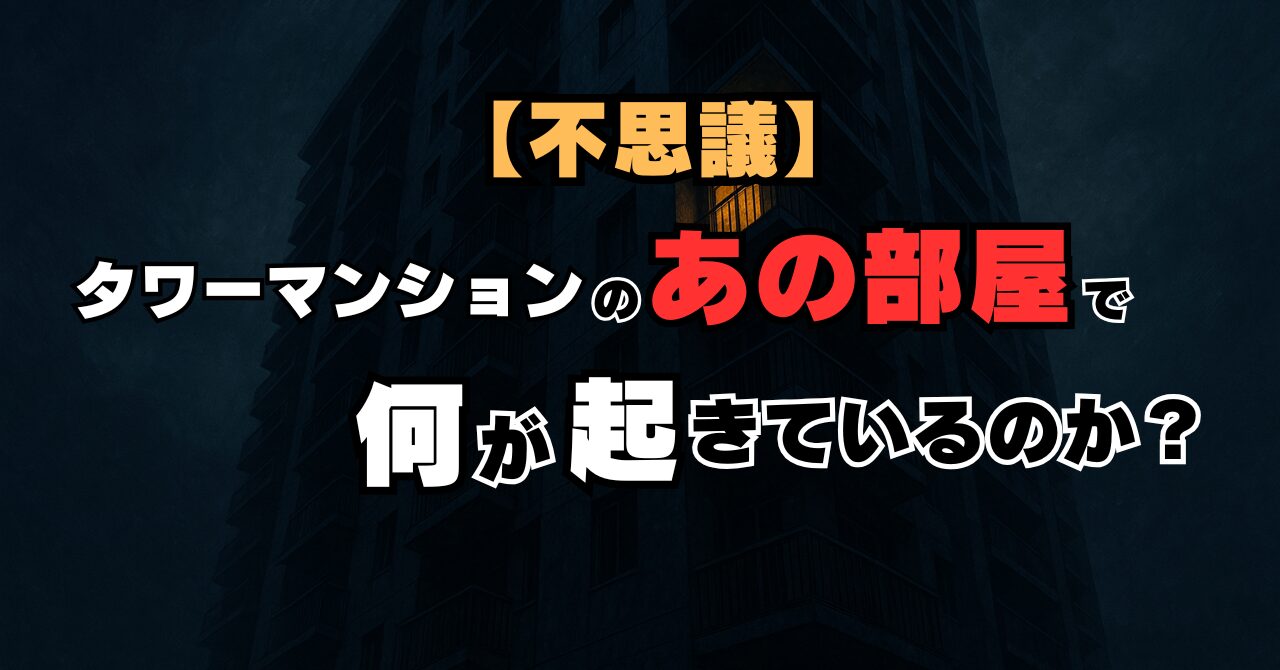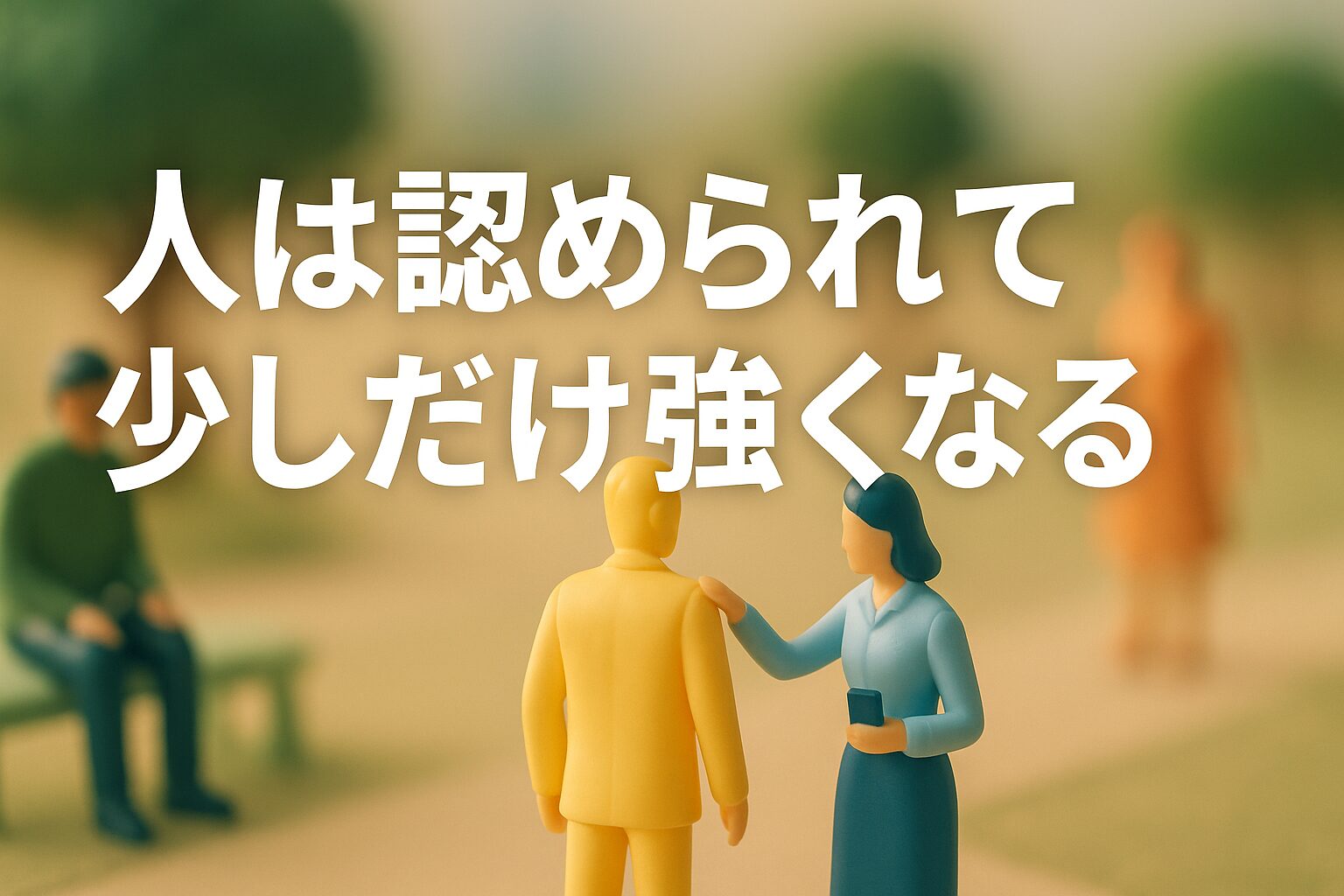将棋クラブはなぜ潰れないのか?〜高齢者の社交、大会・教室収入、低コスト運営、ファン層の厚さ〜

はじめに

なぜか生き残る将棋クラブの謎
日本各地にひっそりと存在している「将棋クラブ」
商店街の二階、公民館の一室、時には温泉街の休憩所。
令和の時代になっても、なぜかしぶとく生き残っています。
いや、正直に言えば“潰れにくい”のです。

スマホゲームや動画配信に押されてもなお、将棋盤の前には人が集まります。
これってなぜでしょうか。
──その疑問を
「高齢者の社交」
「大会・教室収入」
「低コスト運営」
「ファン層の厚さ」
という4つの視点から見ていきましょう。

「将棋クラブは潰れない」説、案外ロジカルなのです。
※本記事はエンターテインメント目的で制作されています。

1. 高齢者の社交ニーズが強すぎる

まず、社会背景を押さえておきましょう。
日本の高齢化率は29.3%(2024年10月時点)。
つまり3人に1人はシニア世代です。
しかも孤独や認知機能低下を防ぐには“人との交流”が必要であることは医学的にも証明されています。

将棋クラブはまさに「通いの場」の代表格です。
地域のシニアがふらりと集まり、「今日は角換わりでいこうかな」なんて言いながら、半日を過ごせます。
頭を使い、手を動かし、人と会話する。
三拍子そろった健康習慣が月数千円で手に入るのですから、これはもう“処方箋のいらないお薬”と言ってもいいでしょう。

若い人からすると「おじいちゃんたち、ずっと同じ相手と指して飽きないの?」と思うかもしれません。
でもそれは筋トレで「毎回同じ腕立てをやって飽きないの?」と聞くのと同じです。
ルーティンこそ強いのです。
2. 大会・教室で安定収入

次に、収益の話です。
クラブはただの「暇つぶしの場」ではありません。
しっかりとキャッシュポイントを持っています。

例えば子ども将棋教室。
初心者向けなら月3,000円前後から、首都圏のしっかりした教室では8,000円/月なんて設定も珍しくありません。
親としては「ゲームばかりやらせるより頭を鍛えてくれるなら安いもの」と考えるのです。

さらに大会。
参加費1,000円〜3,000円程度でも、20人30人集まれば結構な売上になります。
加えてABEMAトーナメントなどの配信イベントは有料チケット5,500円〜で盛況です。
プロ棋士を呼んでの指導対局となれば、数万円単位のギャラが動きますが、それでも人気は高いのです。
つまり、クラブは
「会費」
「月謝」
「大会収入」
「イベント」
の4重奏。
娯楽産業としては驚くほど多角的に収入源を持っているのです。
3. 実はランニングコストが安すぎる

「でも家賃とかで赤字になるんじゃ?」
──ここで意外な事実です。
将棋クラブの運営費って驚くほど安いのです。

公民館の貸し会議室は、午前・午後・夜間それぞれ2,000〜3,000円前後。
参加者が10人集まれば、ひとりワンコインで黒字に転換できます。
将棋盤と駒は耐久財で、10年20年使えます。
飲食店のように食材ロスもありません。
必要なのは畳んでも壊れない折り畳み机と、静かに時間を刻む壁掛け時計くらいです。

クラブの経営者いわく「最大のコストはむしろ冷暖房」とのこと。
つまり電気代がライバル。
おそらく“敵は将棋AIよりもエアコン代”なのです。
4. ファン層の厚さと継続力

さらに忘れてはいけないのが、ファン層の存在です。
最新のデータによれば、将棋の参加率は4.7%。
数字だけ見ると「少なっ!」と思うかもしれませんが、人口に直せば数百万人規模です。
しかもここに「観る将」(指さないけど観戦だけ楽しむ層)が加わります。

ABEMAでの配信や有名なプロ棋士の人たちの活躍で、将棋はむしろライトファンを拡大中です。
カフェでコーヒーを飲みながら野球中継を見るように、「今日は棋聖戦の第3局をABEMAで」なんて人が増えています。

つまり将棋クラブは、参加する人だけでなく“文化の受け皿”にもなっています。
趣味人口+観戦人口、このダブル層があるからこそ、クラブは簡単に干上がらないのです。
最後に

将棋クラブは小さな「生存の達人」
ここまでまとめると、将棋クラブが潰れない理由は明快です。
- 高齢者の社交場としての絶大なニーズ
- 教室や大会での安定収入
- 公民館利用などによる低コスト運営
- “観る将”を含む厚いファン層

この4つがカチッと噛み合っている限り、将棋クラブは“潰れにくい小さな経済圏”として存続し続けます。
ある意味、将棋クラブは時代の風雪に耐える「駒」のような存在です。
取られてもしぶとく持ち駒に戻り、また盤上に復活してくる。
まさに不滅の歩兵と言えるでしょう。

あなたの街の商店街にも小さな将棋クラブがあるかもしれません。
入ってみれば、そこは地域のリビングルーム。
静かな駒音の向こうに、人生の駆け引きが詰まっています。
──将棋クラブは潰れません。
だって、人が指し続ける限り、物語は続いていくのですから。