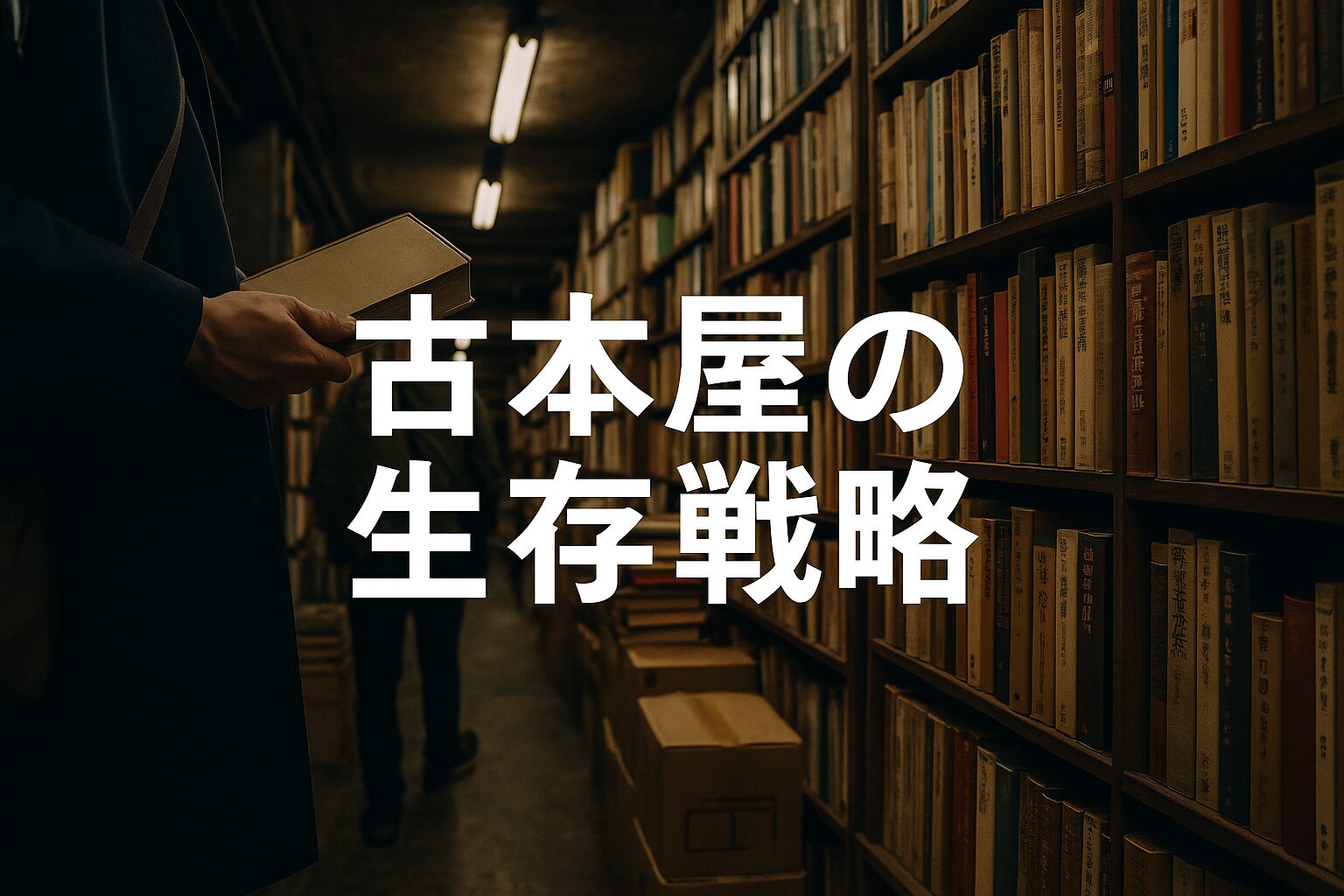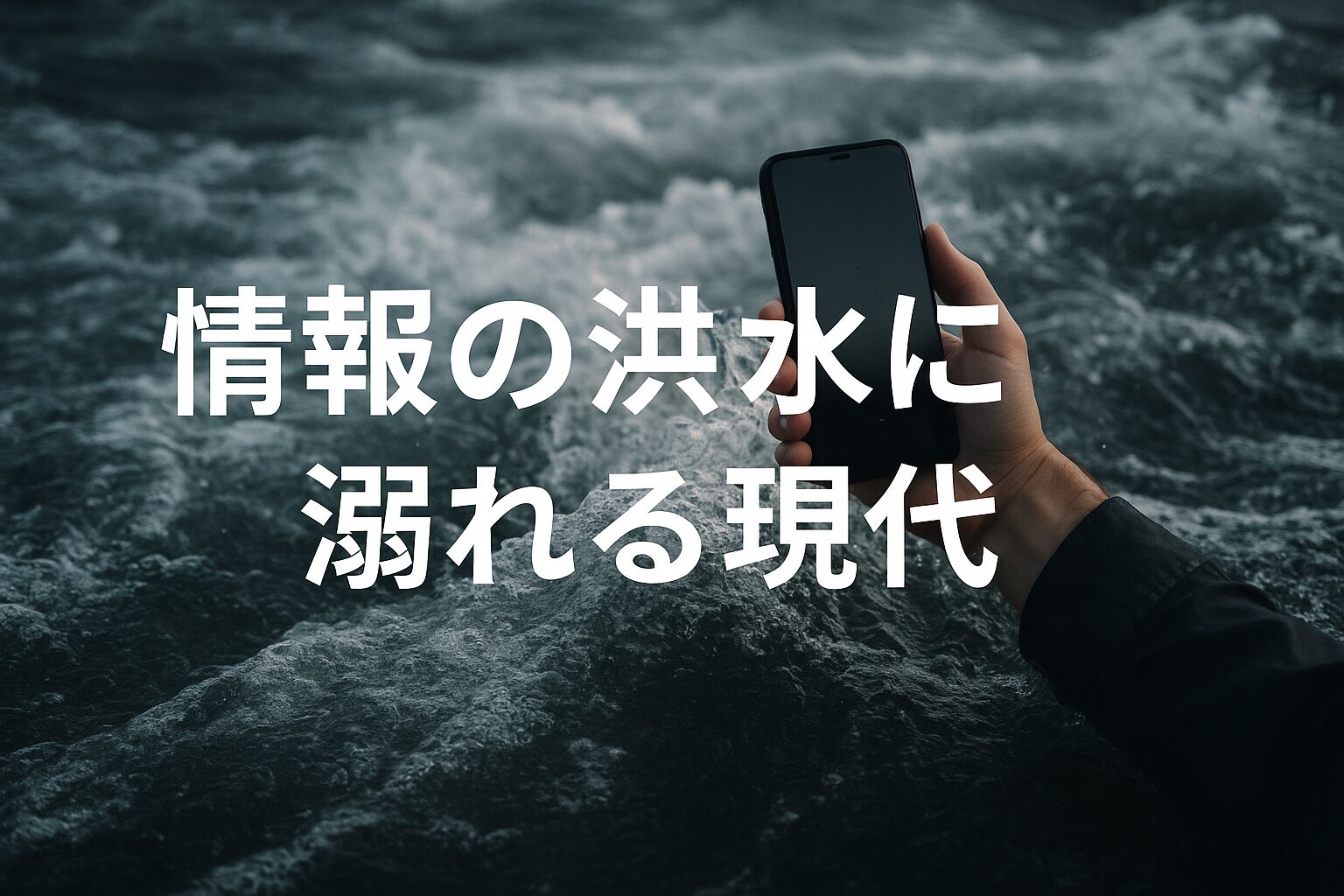なぜ昔ながらの定食屋は潰れないのか?
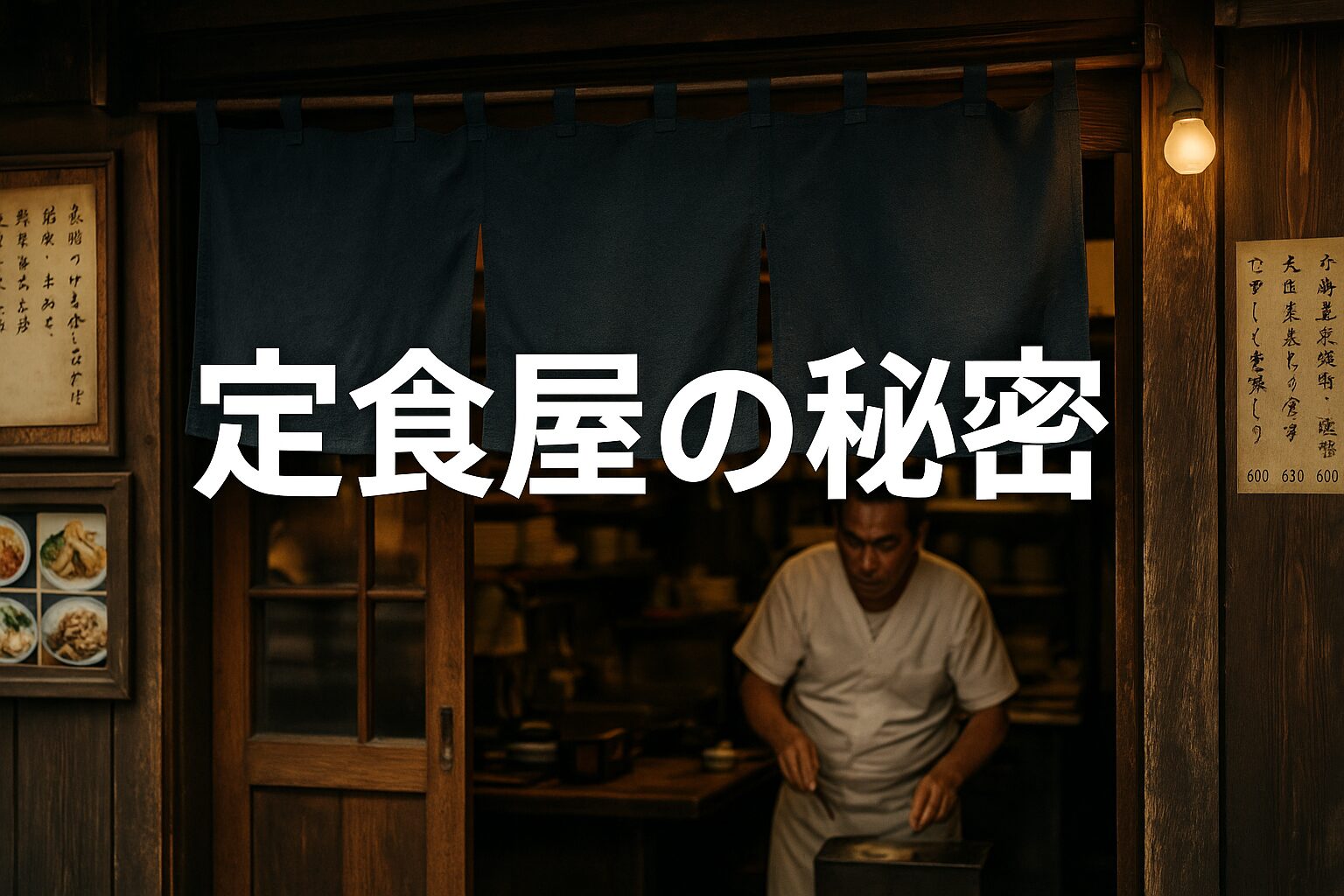
はじめに

街を歩けば、昭和の香りただよう定食屋が今も元気に暖簾を掲げています。
チェーン店が乱立し、Uber Eats が我が物顔で走り回るこの時代に、なぜあの木製メニュー表の定食屋は健在なのか。
今回は、その“生存戦略”をユーモラスに掘り下げてみましょう。
※本記事はエンターテインメント目的で制作されています。
家族経営という最強のコストカット

まずは人件費。
飲食業界の平均人件費率は約40%。
ここをどう削るかで生死が決まります。
そこで登場するのが“無給の家族”です。
息子はフライパンを振り、奥さんは配膳をし、娘はSNSを更新。
外部人件費ゼロ、教育コストもゼロ。
これを「ブラック企業」ならぬ「家族企業」と呼びましょう。
しかも世代交代がスムーズ。
息子が味を継ぎ、娘が接客を継ぐ。
DNAの中に「おふくろの味」が組み込まれているので、引き継ぎコストはほぼゼロ。
スタートアップ界隈が聞いたら泣いて羨む仕組みです。
家賃を制する者が生き残る

飲食店の経営において「家賃比率5〜10%以内」が黄金ルール。
ところが昔ながらの定食屋は“住宅兼店舗”が多い。
1階で揚げ物、2階で洗濯物。
これぞ最強の固定費削減モデルです。
しかも立地は繁華街より商店街。
賃料相場は横ばい傾向で、都心のバブルを尻目に静かに経営を続けられる。
親族所有物件なら家賃ゼロ、いわゆる「無敵の賃貸プラン」です。
常連文化が店を支える

定食屋の暖簾をくぐれば、「いつもの?」の一言。
常連にとってはメニュー表など飾りです。
顔を覚えられ、名前を呼ばれることで「自分はここに属している」という帰属感が芽生えます。
チェーン店のタブレット注文には、この“人情アルゴリズム”は実装されていません。
常連同士の交流、店主との世間話
――これらがサードプレイスとしての価値を生み、売上を安定させます。
つまり“味”だけでなく“居場所”を提供しているんですね。
胃袋と心の両方を満たす二刀流、それが定食屋の必殺技です。
副収入という秘密兵器

コロナ禍で脚光を浴びたのがテイクアウト。
唐揚げ弁当、日替わり惣菜、さらには冷凍餃子や自家製ソースまで。
もはや「食堂」ではなく「総合食料供給センター」
さらに、商工会議所の補助金を活用して新しい設備を導入するケースも珍しくありません。最近では
「料理教室を開く定食屋」
「夜は居酒屋に変身する二毛作店」
なんてスタイルも増加中。
多角化というカメレオン戦略で、売上の谷を埋めているわけです。
とはいえ環境は厳しい

もちろん、全ての定食屋が安泰というわけではありません。
2024年、飲食店の倒産件数は過去最多の894件。
小規模店舗の多くが苦境に立たされています。
平均営業利益率はマイナス域に突入し、まさに“茹でガエル経営”状態。
つまり、残っている定食屋は
「家族経営」
「低家賃」
「常連文化」
「副収入」
という4本柱をフル活用して生き延びている、選ばれし強者たちなのです。
定食屋は文化そのもの

昔ながらの定食屋が潰れない理由は、単なる経営テクニックではありません。
そこには“地域コミュニティ”という見えない資産があります。
おじさんが昼に生姜焼きを食べ、学生が夜にカツ丼をかき込み、子どもが「ただいま」と言ってのれんをくぐる。
そんな日常が文化となり、文化が経済を支えているのです。
チェーン店のカレーもいいけれど、やっぱり「いつもの定食屋」で味噌汁をすすりたくなる。
私たちの胃袋と心を温める定食屋は、今日もまた静かに、そしてしたたかに生き延びています。
最後に

定食屋の生存戦略を一言でまとめるなら
――「固定費を軽く、顧客を濃く」
これぞ究極の経営哲学。
次に暖簾をくぐったとき、いつもの味に感謝しつつ「ありがとう、まだ潰れないでね」と心の中でつぶやいてみてください。