緑なのに“青”と呼ぶのはなぜ?日本だけに残った不思議すぎる色のミステリー

はじめに

日常の“当たり前”は、ある日ふと裏切ってきます
子どものころ、母と手をつないで横断歩道に立っていたときのことです。
信号がチカチカと光り始め、母が言いました。
「ほら、青になったよ。渡るよ〜」
……いや、僕にはどう見ても“緑”なんですけど?
その瞬間、幼い僕の脳内では小さな会議が開かれました。
――議題:「なぜ緑を青と言い張るのか?」

しかし母は平然。
僕のツッコミは虚空へ消えていきました。
あのころは「大人って不思議だな~」と思っていました。
ところがです。
大人になった僕は気づきました。
僕も普通に“青信号”って言ってる。
毎朝すれ違うのに名前を知らないマンションの住人みたいに、違和感をごまかしたまま生き続けていたのです。
気づいたら仲良くなってるタイプ。

でも、実はこの「青信号」という言い回しには、とんでもなく深い事情が隠れていました。言語のクセ、歴史の積み重ね、法律のチカラ、そして国際ルールとのせめぎ合い……。
思ったよりずっとドラマチックなんです。
この、小さな光の色をめぐる物語は。
では、信号が青……いえ、緑……いや、どっちでもいいので、とりあえず進みましょう。
※本記事は筆者個人の感想をもとにエンターテインメント目的で制作されています。
世界基準では「緑」でも日本では“青”が当たり前

まず知っておきたいのは、世界では交通信号の色が 赤・黄・緑 に統一されているということです。
これはCIE(国際照明委員会)が決めた国際的なルールです。
つまり、世界の人に「進んでいい信号の色は?」と聞くと、全員が 「Green!(緑)」 と答えるはずです。
もちろん、日本以外では。
では日本は世界基準を無視しているのかというと、そうではありません。
日本の信号も国際規格に沿ってしっかり“緑”の範囲に入っています。
ただし、その緑の中でも できるだけ青に近い色 を意図的に選んでいるのです。
例えるなら、「髪を染めてはいけません」という校則の中で、黒に近い“ギリギリの茶髪”にしてくる学生のようなものです。
ルールには従っているけれど、最大限自分たちの感覚に寄せている、というわけです。
この時点で、すでに日本らしいクセが出ています。
法律上も正式に「青色の灯火」と呼んでいます

実は、日本で“青信号”が定着した最大の理由は 法律が「青色」と規定しているから です。
道路交通法施行令では、進むことができる信号について明確にこう書かれています。
「青色の灯火は、進むことができることを意味する」
いや、どう見ても緑ですよね? と言いたくなりますが、法律が青と言うのなら、名称としては青になるわけです。
これはもう一般市民が口を挟む余地はありません。
「うちの犬はポメラニアンです」と飼い主さんに言われたけれど、どう見ても柴犬にしか見えない……そんな状況に似ています。
たとえ見た目が違って見えても、名前は名前として決まってしまっているのです。
日本語の「青」はもともと緑まで含む広い言葉です

日本語の歴史を遡ると、さらに面白い事実があります。
古代日本では、色名は「赤・白・黒・青」の4色しかありませんでした。
現代のように細かく色を分類する文化がなかったため、“青”は 青と緑の両方を含む広い意味 を持っていました。
その名残は現代にも残っていて、僕たちも自然と使っています。
- 青葉(=緑の葉)
- 青りんご(=黄緑のりんご)
- 青野菜(=緑色の葉物野菜)
こうして例を並べてみると、「青とは?」と哲学を始めてしまいそうになりますよね。
さらに“緑”という言葉が本格的に色名として独立するのはずっと後の時代です。
“緑”は元々
「芽吹き」
「みずみずしさ」
を表す言葉でした。
東北大学の研究でも、日本語の青と緑の境界が他言語に比べて曖昧であることが示されており、この問題は単なる言葉遊びではなく、深い文化的背景に支えられていることがわかります。
言葉と国際ルールの折衷案で日本だけ残りました

1930年、日本で初めて自動交通信号が設置されたとき、国際ルールではすでに「緑」が進行の色と決まっていました。
しかし当時の日本語話者にとって、その色は“緑”というより “青の一部” と認識されていたと言われています。
今よりも“青”の意味範囲が広かったのです。
さらに決定打となったのが、当時の新聞報道でした。
白黒写真しかなかった時代、記者が信号を“青信号”と記述したことで、その呼び方が一気に広まってしまいました。
そして1947年。
一般に浸透した言い方に合わせる形で、法律の表記まで 「青色の灯火」 に変更されました。
こうして日本では、
- 実際の色:緑寄りの青緑
- 法律上の呼び名:青色の灯火
- 日常語:青信号
という二重構造が成立したまま、現代まで続いているのです。
脳科学の話:人間は青と緑をちゃんと区別できます

「言葉が曖昧なら、色の見分けも曖昧なのでは?」と思うかもしれません。
しかし、脳科学の研究では 生後6ヶ月の赤ちゃんでも青と緑を区別できる ことがわかっています。
つまり、色の違いを知覚する能力は言語習得より前に備わっているのです。
ではなぜ“青信号”と呼んでしまうのかというと、単に 言葉の習慣が強く残っているから にすぎません。
人間関係でも似たことがありますよね。
「付き合っているんですか?」と聞かれて「いや、そういうわけじゃないんだけど」と答えつつ、毎週デートをしている二人のようなものです。
客観的には“緑”なのに、呼び名だけ“青”のままにしている状態です。
最後に
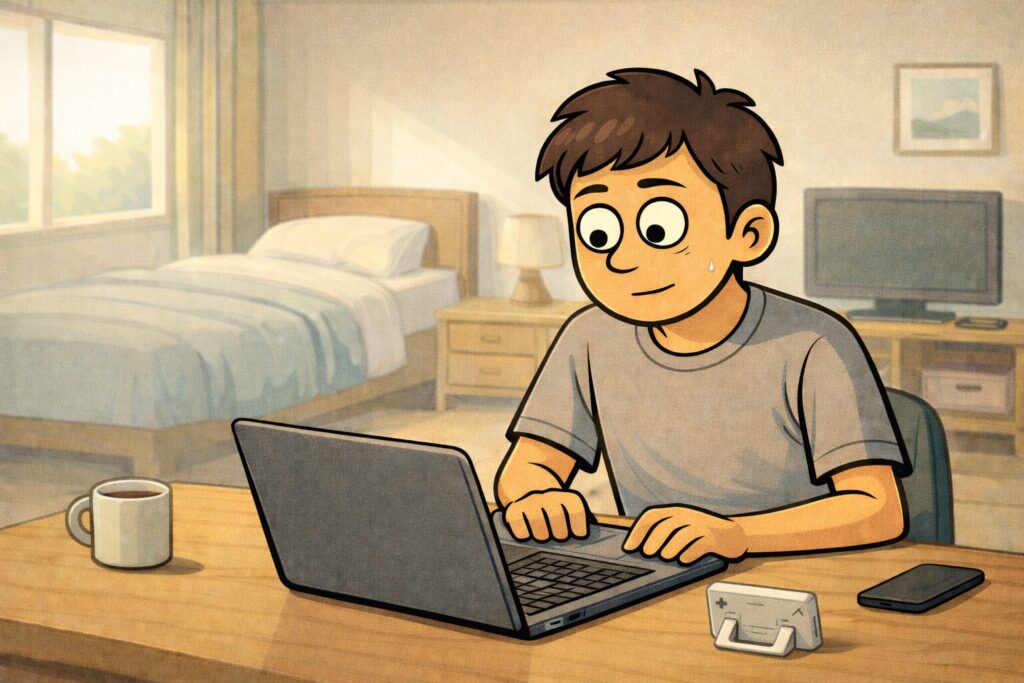
青信号という言葉は、日本語の歴史を背負った文化遺産です
結局のところ、信号の色そのものは“緑”なんです。
いやもう、どう見ても緑。
もしあれを青と言うなら、僕の黒髪も「ダークホワイト」って呼んでいいですか、ってレベルです。
それでも日本人が“青”と呼び続けているのは、長い言語の歴史と、容赦なく青と書き続けた法律の力が合体した結果なのです。
いわば、自然発生した“文化コンボ”です。

つまり「青信号」という言葉は、日本語の独特な色彩感覚が積み重なってできた 小さな文化遺産 なんですよね。
奈良の大仏ほどの威厳はありませんが、日常にこっそり紛れ込んだ文化財です。
海外の人からすると「え、色弱なの?」と心配されるかもしれません。
でも僕たちは堂々と言ってもいいのです。
だって、
見えている色と、言葉がつくる世界がズレていてもいいじゃないか。
日本語だもの。

最後に、あの日の母の言葉。
「青になったから渡るよ」
いやいや、僕は確かに緑を見ていたんですよ?
でも母にとってはそれが“青”だった。
そして今の僕も、堂々と“青信号”と言ってしまっています。
立派な代々続く青信号家系です。
つくづく思います。
言葉って、ただの表現じゃなくて、文化や記憶、そしてちょっとしたクセまで背負っているんだなと。
今日もまた、緑色の光に「行け行け」と背中を押されながら、そっと青信号を渡っていくのです。







