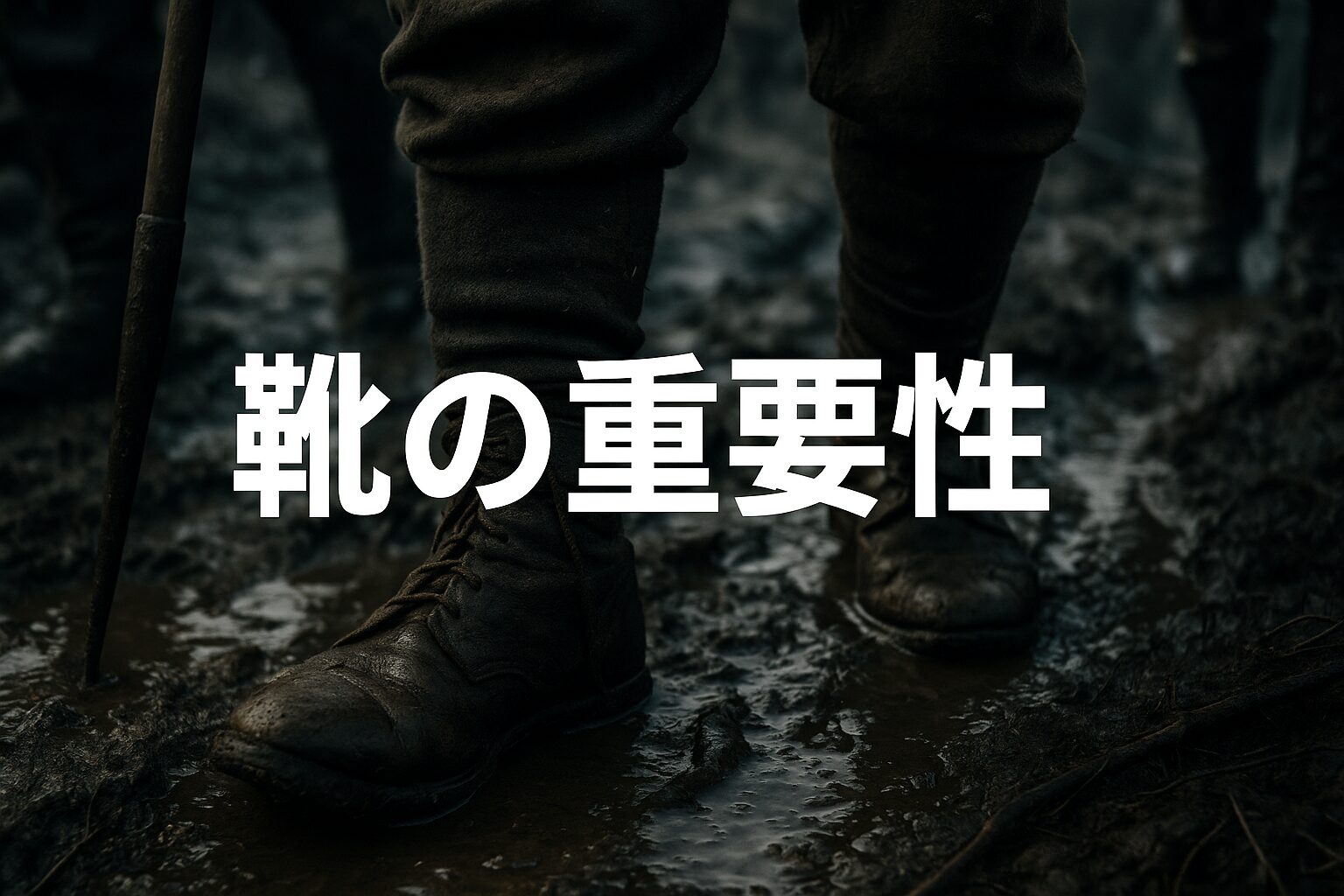戦いはここからが本番だった――中世歩兵が担った“戦後処理”のリアル

はじめに

「よし、勝った! あとは打ち上げだ!」
…と言えたらどれだけ楽だったか。
中世ヨーロッパの歩兵たちにとって、戦闘の終了は
「今日の業務はここまで」ではなく
「はい、ここから残業フルコースです」
の合図でした。
※本記事は筆者個人の感想をもとにエンターテインメント目的で制作されています。
「戦いが終わったあと」こそ始まる歩兵の仕事

派手な戦闘シーンは、映画でもゲームでも主役です。
でも、実際に時間と労力を大量に吸い取るのは、そのあと。
・戦場に散らばった遺体や装備の片づけ
・略奪とその“ルール”
・捕虜の扱い
・焼けた町や踏み荒らされた畑の後始末
こういう“地味だけど誰かがやらないといけない仕事”の多くを押しつけられたのが、
まさに歩兵たちでした。
現代の会社でいうと、
プレゼンで拍手を浴びるのは上司だけど、
資料づくり・後片づけ・議事録は全部こっち、みたいなポジション
と思ってもらうと早いです。
戦死者の埋葬と略奪の実態

「名もなき兵」と「VIP」の差は、死んでからもデカかった

まずは戦死者の埋葬から見てみましょう。
キリスト教社会の中世ヨーロッパでは、
「ちゃんと土に埋葬すること」は宗教的にとても大事な行為でした。
教会法の世界では、
- 最後の祈り
- 葬儀ミサ
- 聖別された土地(教会墓地など)への埋葬
こうした一連のセットが、魂の救済に関わる大イベントとされていたんです。
ただし、ここで大問題がひとつ。
戦場には、そんな儀式を丁寧にやっている余裕がほぼない。
さらにもうひとつ。
しかも「誰の遺体か」がわかるレベルで管理できるのは、ほぼエリートだけ。
実際、タウトンやヴィスビューといった中世の有名な戦場跡では、
発掘調査の結果、一般兵と思われる遺体がぎゅうぎゅう詰めの集団墓地から大量に見つかっています。
- 遺体は肩を寄せ合うように押し込められ、
「敬意を込めて並べました」ではなく「スペースがないので詰め込みました」のノリ。 - 鎧を着たまま埋葬された遺体も多く、
「数が多すぎて、全部脱がせてる暇なかったんじゃ…」と研究者に言われる始末。

一方で、騎士や貴族などのエリートはどうかというと、
- 遺体を故郷まで輸送して、
- 教会の中や特別な墓所に埋葬し、
- 時には立派な墓碑や彫像まで建ててもらう
というVIPコースが用意されていました。
同じ戦場で死んでも、
「名も残らない穴」か
「名前と家系が刻まれた墓石」か
それくらいの差が、死んでからもはっきりついてしまう社会だったわけです。
「略奪はダメです(と言いつつみんなやる)」という世界

戦場の遺体からは、当然ながら使えるものは全部はぎ取られます。
- 武器や鎧
- ベルト、装身具、靴
- ちょっとした金属パーツまで
考古学的には、「遺体にほとんど装備が残っていない=事前に徹底的に略奪された」と判断されます。
ところが、です。
王や皇帝が出した軍規(オーディナンス)を読むと、
- 教会や聖職者を略奪するな
- 農民や子どもを襲うな
- 教会に火をつけたら死刑になるぞ
など、かなり真面目な「反・略奪ルール」が並んでいます。
ここでツッコミどころ。
そんなに何度も禁止を出すってことは、
みんな普通にやってたってことでは?

そう、まさにその通りで、
「建前としては略奪NGだけど、現場では『まあ、ほどほどにな…』」という空気だったと考えられています。
特に歩兵たちにとって、略奪は
- 給料が安いorそもそも支払いが不安定な中での
- ほぼ唯一の“ボーナス”
でもありました。
そりゃあ現場としては、「やめてください」と言われても簡単にやめられないわけです。
捕虜の護送と「交渉の手伝い」

投降にも「お約束のジェスチャー」があった

中世ヨーロッパでは、「降伏にもルール」がありました。
年代記や研究によると、よく出てくるのがこんなジェスチャーです。
- 武器を地面に落とす、あるいは柄を手前にして敵に差し出す
- 片膝をつく、両手を上げる
- 「降伏します」にあたる決まり文句を口にする
このセットをやることで、
「まだ抵抗する敵」から
「殺さずに利益を生む“捕虜候補”」へ
ステータスが切り替わります。
ここで重要なのが、身分による扱いの差。
- 騎士・貴族・お金を持っていそうな傭兵
→ 高額の身代金が期待できるので、生きて捕らえたい - 一般歩兵・農民兵
→ 身代金の見込みがほぼないので、殺される/放置される/こき使われる…など扱いがバラバラ
命の値段が階級で決まってしまう、かなりシビアな世界です。
捕虜護送という「地味に責任重い仕事」

さて、誰かが偉い騎士を捕らえたとします。
じゃあ捕らえた本人(エリート騎士)がずっと付きっきりで護送するか?
というと、そんなことはあまりありません。
護送・監視を任されるのは、多くの場合下級兵士=歩兵たちです。
- 戦場から城や都市までの長距離護送
- 牢獄や城の塔、修道院などでの見張り
- 出入りの管理や食糧配給の監督
こうした“雑務のようでいてミスれない仕事”を請け負うのが彼ら。
もし捕虜に逃げられたら、
「あの高額案件、どこやった!?」
と責任が問われるのは、現場で見張っていた歩兵のほうです。
現代で言うと、「重要なVIP顧客のデータをまちがって消したバイト」みたいな状況。怖い。
さらに、身代金交渉のために捕虜が移動するときには、
- 誰がどこまで付き添うか
- どのルートで移動するか
といったことが文書に細かく書き込まれますが、 その付き添い役として動くのもまた、歩兵レベルの人々でした。
華やかな「騎士の決闘」の裏側で、
地味な移動・警備・書類どおりの運用を黙々とこなす人たちがいた、というわけです。
荒れ果てた土地での「復興支援」

復興=オシャレなプロジェクトではなく「穴掘りと石運び」

戦争が終わると、戦場だけでなく、その周辺の町や村はボロボロです。
- 焼かれた家
- 破壊された橋や城壁
- 荒れた道路
- 放置された死体と家畜
現代でいう「復興支援チーム」みたいなNPOはもちろん存在しないので、
ここでも動員されるのは、兵士・元兵士・地元民でした。
特に重要なのが、防衛インフラの再建。
- 城壁の修理・増築
- 城や砦の補強
- 壊れた橋の再建
- 城門前の道路整備
こういった工事を支えるために、
イングランドなどでは
「murage(城壁税)」
「pavage(道路税)」
「pontage(橋税)」
といった通行税が課されていました。
で、その税金で雇われるのが、
石工、大工、一般労働者、そして解雇された兵士たち
という構図です。
「兵士」でもあり「穴掘り人足」でもあり「農民」でもある

多くの歩兵は、平時はふつうの農民や都市民です。
戦争になれば徴兵され、戦が終わればまた畑に戻る――
…だけでは終わりません。
- 城壁の維持管理や堀の掃除が「市民の義務」になっている都市も多く、
- 「兵役」と「土木労働」がセットで課されるケースも少なくなかったと考えられています。
さらに、南ネーデルラントでは「ribalds(リバルド)」と呼ばれる下層の軍属・従者たちが、
- 荷運び
- 汚物の清掃
- 包囲戦での土木作業
- 死体処理
といった“誰もやりたくないけど絶対必要な仕事”を一手に引き受けていました。
いわば、
戦時:歩兵兼なんでも屋
戦後:土木作業員兼清掃員兼治安維持要員
通年:農民 or 町人
という、マルチタスクにもほどがある働き方です。
歩兵の「戦後処理」から見えてくる人間社会のクセ

ここまで見てくると、中世ヨーロッパの歩兵の「戦後処理」って、なかなかエグい仕事のセットですよね。
- 名も残らない戦友の埋葬
- 自分たちの生活費にもなるけれど、建前上は禁止される略奪
- 絶対ミスれない捕虜の護送・警備
- 城壁や橋、道路の復旧作業
- そして、また次の戦争に備える準備……
もちろん現代の私たちは、
戦場で死体を埋めたり、捕虜を護送したりするわけではありません。
でも、
- 誰かがやらないと回らない「裏方仕事」
- 派手さゼロなのに責任だけ重いタスク
- きれいごとの裏で、現場が泥をかぶっている構図
こういうものは、今もあちこちに残っています。
たとえば会社の中でも、
- 細かい調整や後片づけをしている人ほど、名前は表に出にくい
- でも、その人たちがいないとプロジェクトは回らない
ということ、心当たりありませんか?
最後に

「戦が終わったあと」を想像してみる
中世の物語やゲームでは、
クライマックスの合戦が終わると、場面はすっと切り替わります。
画面が暗転して、「数年後――」みたいな。
でも現実には、その暗転のあいだに、
- 穴を掘り、
- 死者を運び、
- 道を直し、
- 城を補強し、
- 荒れた畑を耕し直し、
- そしてまた働くために立ち上がった人たちがいました。
その多くは、名も残らない歩兵や農民たちです。

もし歴史ものの物語に触れるとき、
クライマックスの戦いが終わったあと、
「このあと、誰がどうやって片づけたんだろう?」と一瞬だけ想像してみてください。
それだけで、中世ヨーロッパは少しだけ
「遠い世界のファンタジー」から
「自分とさほど変わらない人間たちが生きていた現実」に近づいてくるはずです。
そして、今日あなたがこなした雑務や裏方の仕事も、
きっとどこかで、誰かの「物語の後始末」を支えているのかもしれません。
その意味では、
私たちもみんな、少しだけ中世の歩兵に似ているのかもしれませんね。
おまけの4コマ
」-384x1024.jpg)