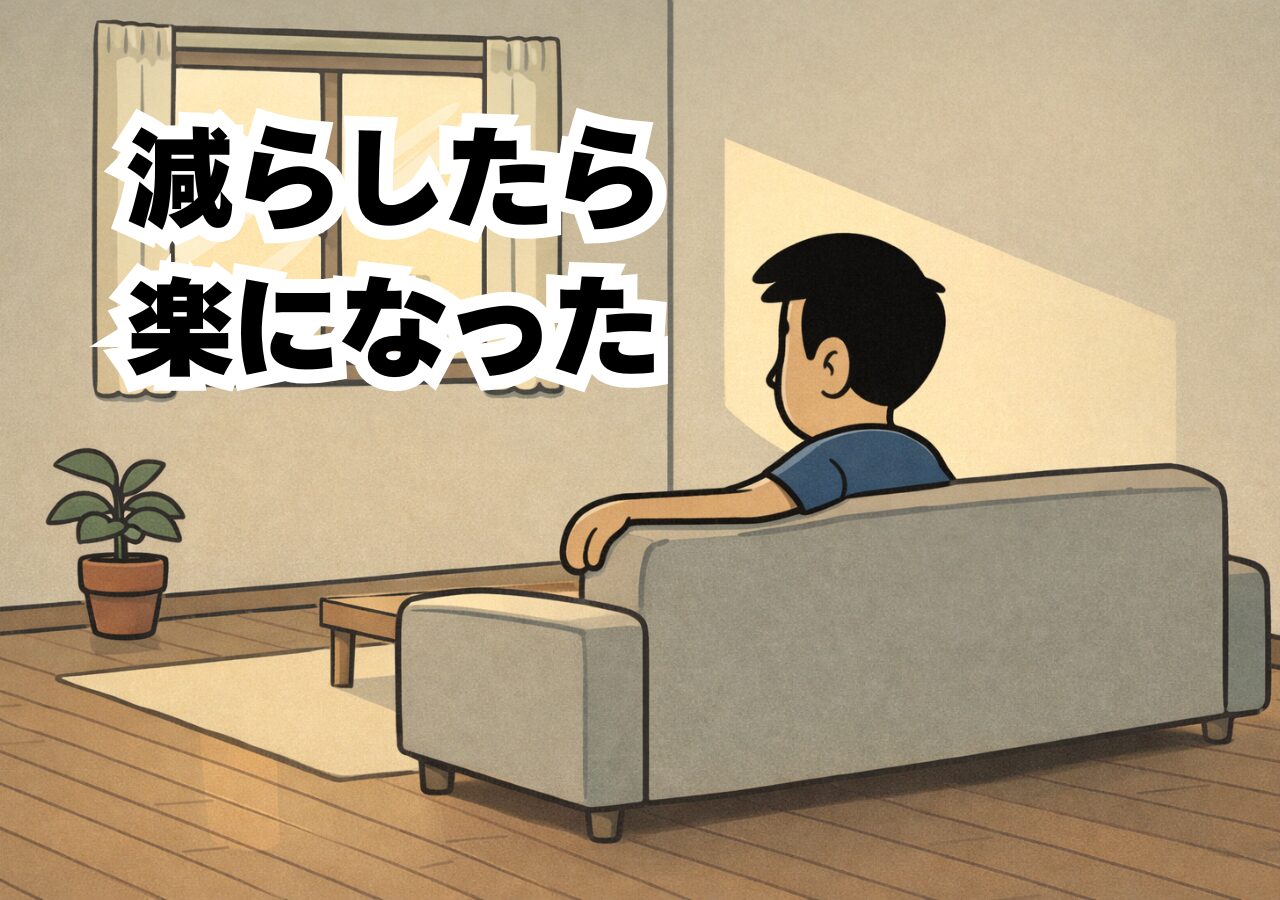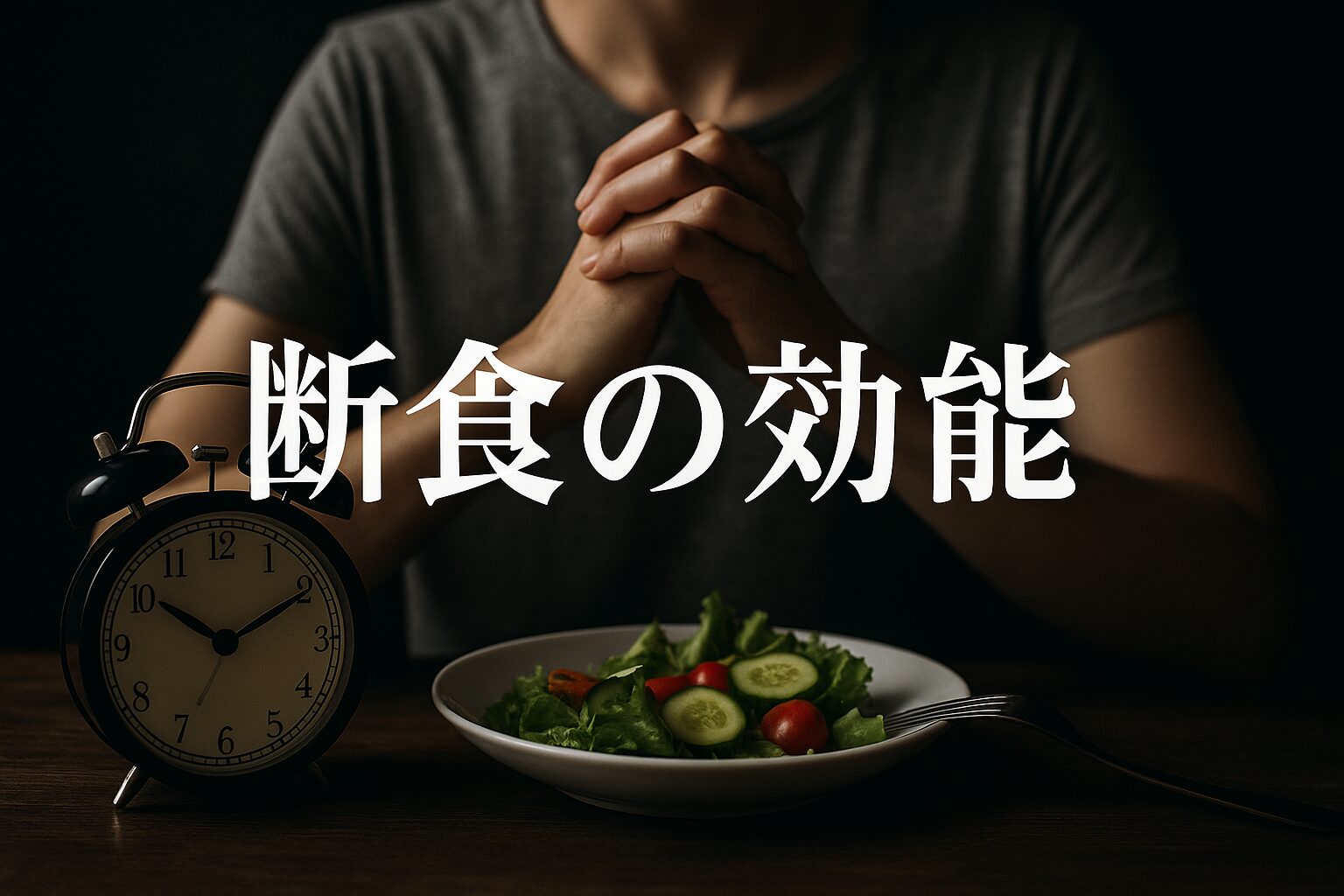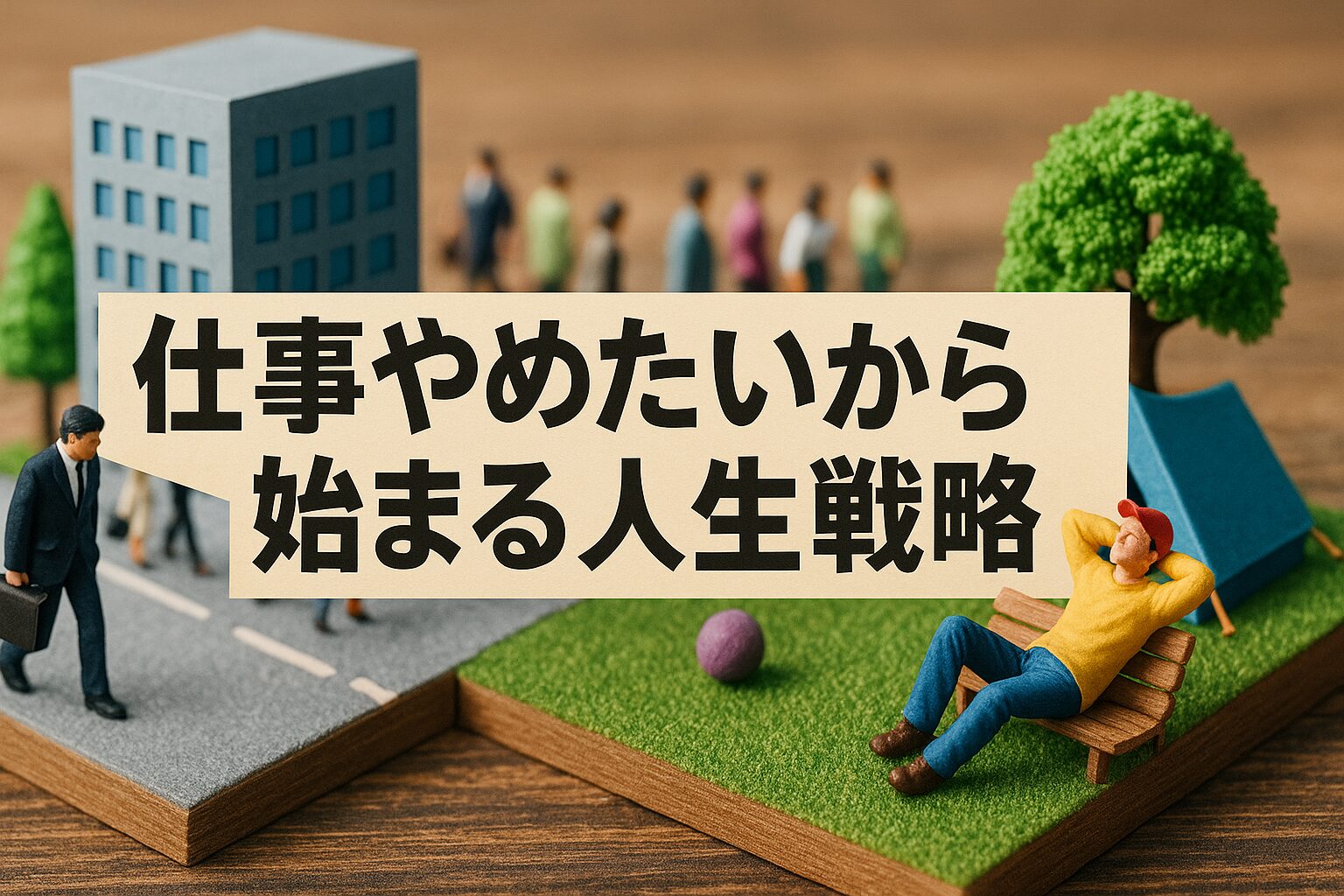学校が教えてくれない「お金の真実」——知らないままで本当に大丈夫?
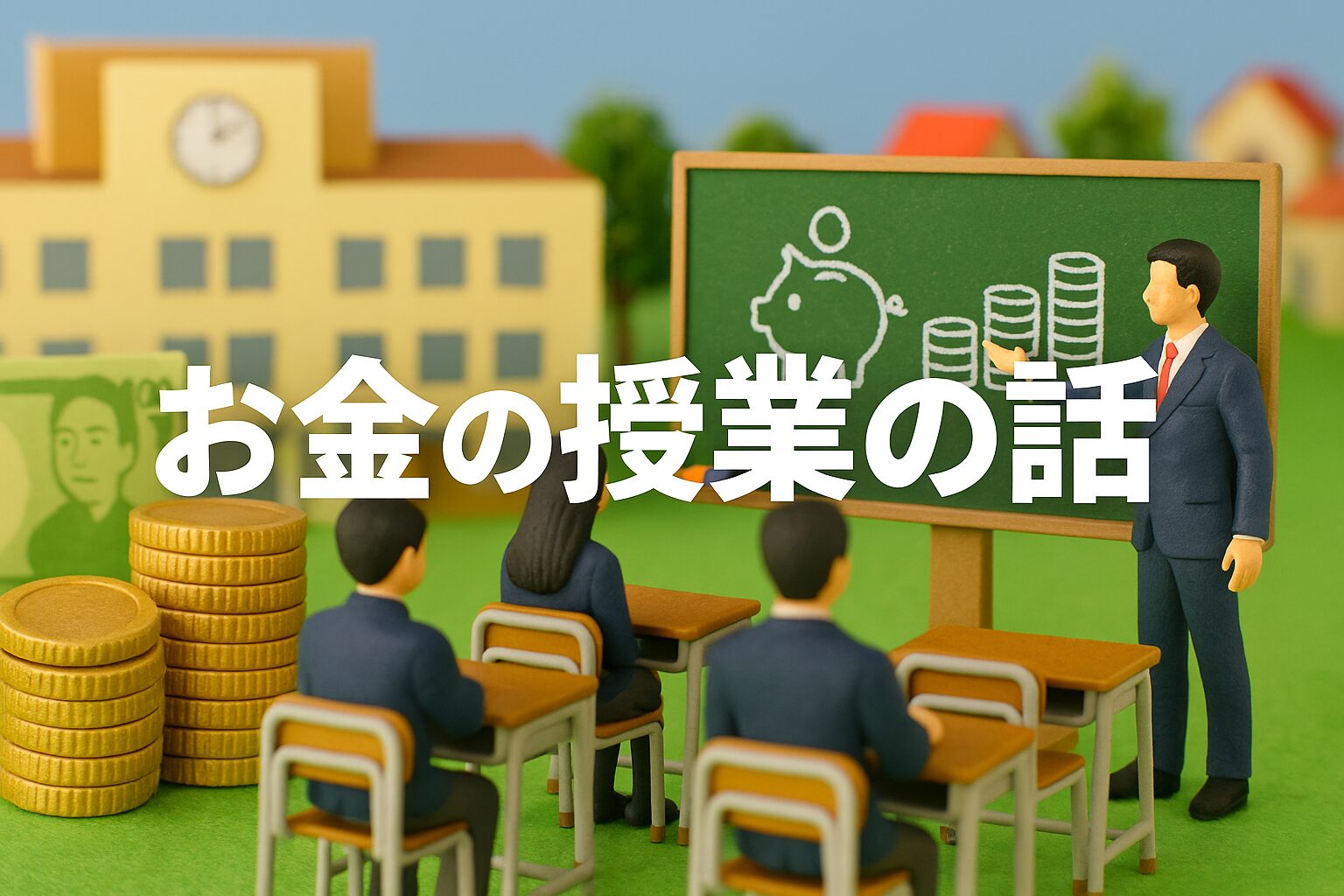
はじめに

最初に少しショッキングな話をします。
実は日本の学校は「お金の授業をまったくしていない」わけではありません。
2022年度から高校の家庭科では資産形成が正式に授業に組み込まれ、株式や投資信託まで扱うようになっています。
とはいえ、SNSをのぞけば今も「なんで学校はお金のことを教えないんだ!」という声があふれています。

なぜ、制度は進んでいるのに、社会の実感はこんなにズレているのでしょうか。
その理由はシンプルです。
制度が動いても、人の意識や文化はすぐには変わらないからです。
先生たちは新しい内容を教えようと奮闘しながらも、自信や時間が足りずに立ち止まっています。
そして多くの人が、まだ「お金を学ぶこと」に抵抗を持っています。
けれども——その壁の向こうには、自由に生きるための知恵が待っています。
ここからは、その壁をどう越えるか、一緒に考えていきましょう。
※本記事は筆者個人の感想をもとにエンターテインメント目的で制作されています。
2025年11月現在の情報で執筆されています。
財布より先に心が閉じている?

「お金の話って、ちょっと下品じゃない?」
——そんな言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
日本では長いあいだ、
「お金の話=いやらしい」
「お金に執着するのはみっともない」
という空気が流れてきました。
その結果、財布よりも先に心のほうが閉ざされてしまったのです。

たとえば家庭でも、子どもにお小遣いの使い方を教えるより「貯金しなさい」とだけ言って終わる。
職場でも、給料や投資の話はタブー。
これではお金の知識が育つわけがありません。
そんな“沈黙の文化”は、学校にも深く染み込んでいます。
教師が授業で投資や保険の話をすると「それ、勧誘じゃないですか?」と誤解されるリスクがあります。
だから多くの先生は慎重にならざるを得ません。
そして慎重すぎて、結局「触れないほうが安全だ」という判断になる。
結果、教室には“お金の話禁止エリア”が自然発生してしまうのです。

でも、考えてみてください。
お金の話を避けることは、人生の話を避けることと同じです。
どう稼ぎ、どう使い、どう守るか。
それは生き方そのものです。
お金の話をタブーにしてきた私たちは、実は自分の未来からも目を背けてきたのかもしれません。
制度は前進、でも教室は渋滞中

2018年に改訂された学習指導要領によって、2022年度から高校の家庭科では
「資産形成」
「リスクとリターン」
「株式・投資信託」
が正式に授業に組み込まれました。
成年年齢も18歳に引き下げられ、クレジットカードやローン契約を自分の意思で結べるようにもなりました。
つまり、もはや「知らなかった」では済まされない時代に入ったのです。
金融教育は、保健体育と同じくらい必修レベルと言っても過言ではなくなったのです。

2024年にはJ-FLEC(金融経済教育推進機構)が設立され、金融庁の教材も一気に充実しました。
「金融庁 高校 指導教材 ダウンロード」と検索すれば、政府公式の資料がすぐに見つかります。
制度の整備は確実に前進しているのです。
しかし
——肝心の教室では、信号が青になっても動き出せない車列のように“渋滞”が起きています。

教員の約半数が「専門知識が足りない」と感じており、投資、税金、社会保障、NISA、インフレ……次々に変わる情報を追うだけで手一杯。
授業の準備どころではありません。
さらに、学校のカリキュラムはすでにパンパンです。
SDGs、情報モラル、消費者教育など、時代に合わせて新しいテーマが次々に増えていく中で、「じゃあお金の授業はどこに入れる?」という悩みが山積みなのです。
まさに、制度の車線は広がったのに、運転する先生たちの燃料と時間が足りない——それが今の教育現場のリアルです。
「中立性」という名のハードル

金融教育にはもう一つの大きな壁があります。
それが中立性です。
授業で特定の金融商品や投資手法を例に出した途端、「それって宣伝じゃないの?」と誤解されてしまうリスクがあるのです。
そのため先生たちは、商品名ではなく“お金と向き合う力”そのものを教える方向へと舵を切っています。
つまり、「何を買うか」ではなく「どう考えるか」を育てる授業へと進化しているのです。
このアプローチは、単なる“儲け話”を超えた判断力を鍛えるトレーニングとなります。

たとえば、
「手数料や税金をどう見積もるのか」
「リスクとリターンをどう比較するのか」
——その思考のプロセスこそが、一生使える武器になります。
金融教育とは、数字を覚える授業ではなく、“生き方を設計する授業”なのです。

そして海外を見ても、このテーマは共通の悩みを抱えています。
イギリスでは2014年に金融教育を必修化しましたが、外部講師の質や企業との関係性にばらつきが出てしまいました。
アメリカでは州ごとに個人金融(Personal Finance)を独立科目として導入する動きが加速していますが、教材や教師の育成が追いつかないという課題もあります。
つまり日本も、「家庭科で触れたから終わり」ではなく、信頼できる仕組みと時間をどう確保するかが次のステージに来ているのです。
金融教育のゴールは“誰かに教えられること”ではなく、“自分で考えられるようになること”。
その一歩を、いま教室も、社会も模索しているのです。
世界の中で見た“お金の授業”の必要性

OECD(経済協力開発機構:世界各国の経済や教育などを研究・比較する国際機関)の調査によると、世界の成人のうち、金融リテラシーの最低ラインに到達している人はたったの3割程度しかいないとのこと。
デジタル金融に関しては、理解度がさらに低いのが現実です。
そして日本も例外ではなく、複利やリスク分散といった基本的な概念すら知らない人が大半を占めています。
お金が日常の中心にある時代に、これほど多くの人が“お金の仕組み”を理解できていない
——それは世界共通の課題なのです。

けれども、ここで少し明るい話もあります。
日本では小学校・中学校・高校と段階的に金融教育が導入され、ようやく“上りエスカレーター”が動き始めたのです。
まだ1階かもしれませんが、確実に未来へ向かって上がっています。
焦る必要はありません。
大切なのは、乗り続ける勇気です。
高校の授業ではすでに、生活に直結したテーマが扱われています。
「初任給を何に使うか」
「留学費用をどう貯めるか」
「NISAをどう始めるか」
——どれも教科書には載っていないけれど、社会に出てすぐに役立つリアルな知識です。
これらはテストの点数にはならないかもしれませんが、人生の点数を確実に上げてくれる勉強です。
最後に

問いを“次のステージ”へ
「なぜ学校はお金を教えないのか?」
——その疑問は、もう嘆くだけの話ではなくなりました。
これから私たちが向き合うべきは、
「どうすればお金を実践的に学べるのか」
「どうすれば誰でも理解できるようになるのか」
という“次の問い”です。
制度は整い、現場も少しずつ動き出しています。
残るのは、私たち一人ひとりが学び手として動き出す勇気です。

大きなことをする必要はありません。
派手な投資もいりません。
複利は時間の味方です。
今日のほんの小さな行動
——千円の積み立てや、一冊の本を読むこと——
が、未来のあなたに驚くほどの違いをもたらします。
学校のチャイムが鳴っても、人生の授業は終わりません。
スマートフォンを閉じたその瞬間から、あなたの“お金の学び”が始まります。
そしてその学びが、未来のあなたを自由にする力になるのです。