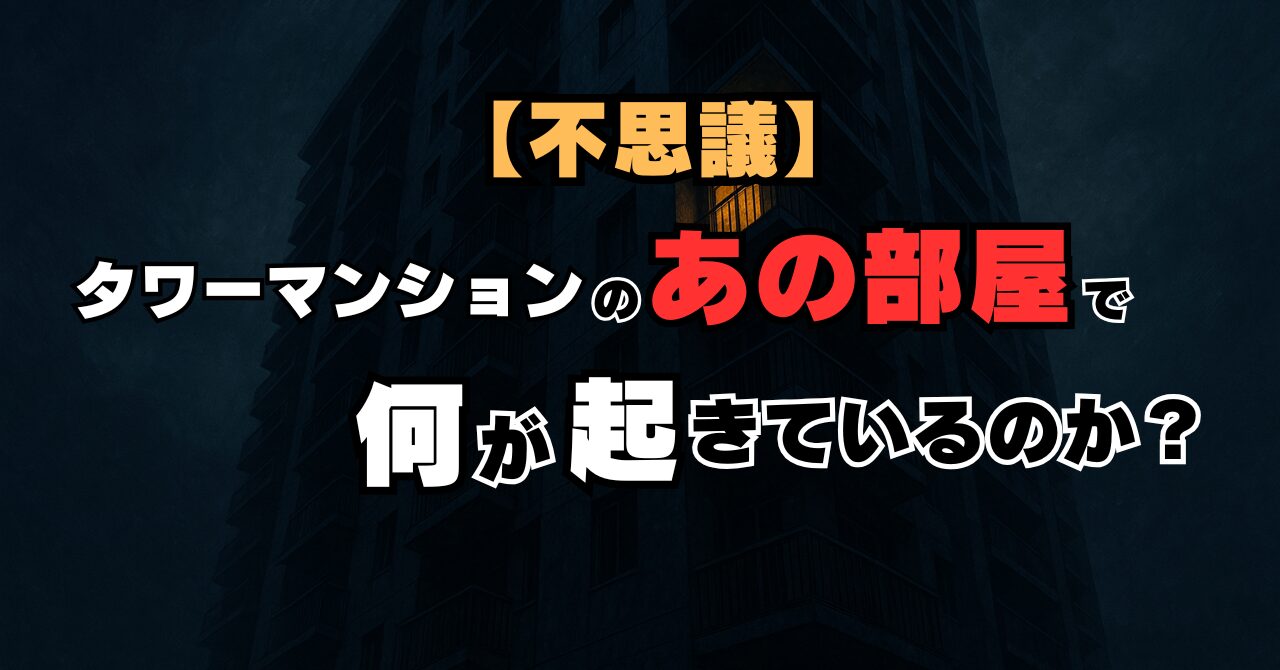駄菓子屋はなぜ潰れないのか?――昭和レトロの生存戦略
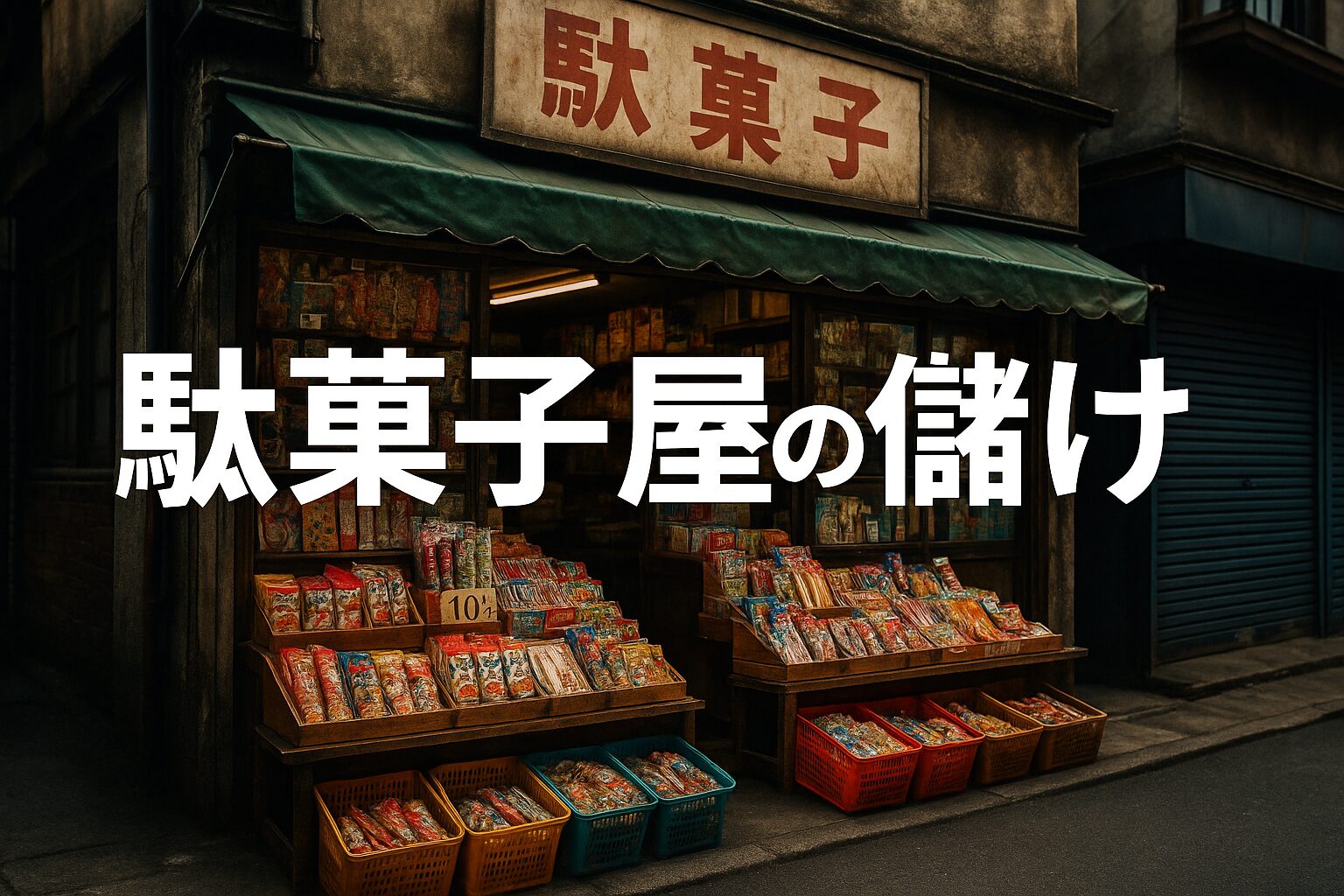
はじめに

街角にひっそりと佇む小さな駄菓子屋。

コンビニの進出、少子化、そして物価高と、逆風の要因には事欠かないのに、完全に消えてしまうことはありません。

まるで「絶滅危惧種なのに意外としぶとい動物」のように、生き残り続けています。
本記事では、その不思議な生命力の理由を探っていきます。
※本記事はエンターテインメント目的で制作されています。

100円で選ぶ幸せ――子ども文化の強さ

定番の「うまい棒」は、2022年に10円から12円に、さらに2024年10月には15円へと値上げされました。
それでも子どもたちは買い続けています。
理由は簡単で、駄菓子は「食べるもの」である以上に「体験するもの」だからです。

100円玉を手に、どれを選ぶか悩む時間はまるで投資のシミュレーション。
失敗しても損失は数十円程度。
子どもたちは選択と後悔、再挑戦を繰り返しながら「消費の練習」をしているのです。

そして大人にとっては懐かしさを呼び覚ますタイムマシン。
SNSでは商品の終売情報(販売終了の告知やニュース)がトレンド入りすることもあり、駄菓子は小さくとも文化的な存在感は大きいのです。
サードプレイスとしての駄菓子屋

地域コミュニティの守護神
家庭でも学校でもない「第3の居場所」
駄菓子屋はまさにその条件を満たしていると研究で指摘されています。

曖昧で、自由で、気軽に立ち寄れる
――その曖昧さこそが魅力となるようです。
子どもは宿題を広げたり、カードゲームに夢中になったり。
大人は世間話を交わしながら地域のつながりを感じます。

近年では、NPOや自治体と連携し「子ども食堂」や「学習支援の場」を兼ねる駄菓子屋も増えています。
つまり駄菓子屋は、安いお菓子を売る場所にとどまらず、地域のインフラを担う“社会装置”へと進化しているのです。
薄利でも続けられる秘密

低コスト経営のカラクリ
「10円の駄菓子でどうやって利益を出すの?」と疑問に思う方も多いでしょう。実際、粗利は10〜20%程度。
10円の商品で利益は2円程度という話もあります。
聞くだけでは夢も希望もないように思えますが、ここにカラクリがあります。

多くの駄菓子屋は自宅の一角や空きスペースで営業しています。
家賃はゼロ、人件費も家族経営でほとんどかかりません。
1日の売上は5,000〜1万円、利益は500〜1,000円程度でも、固定費が少ないため赤字になりにくいのです。
つまり、お金を稼ぐ場所というより「お金をかけずに楽しむ場所」として成立しているのです。

これはある意味、究極のエコ経営。
もしコンビニが同じ利益率で運営すれば即撤退でしょう。
駄菓子屋の強みは「大きく稼がない代わりに、小さく続けられる」点にあるのです。
実は副業――趣味と実益のハイブリッド

駄菓子屋の収益だけで生活できるかといえば、その答えはほぼNOです。
年収にすると100〜200万円程度、つまり副収入レベル。
だからこそ、本業+駄菓子屋というスタイルが一般的なのです。

年金暮らしのおばあちゃんが趣味として続けたり、平日は会社員、週末は店主という二刀流だったり。
最近では、駄菓子屋をベースに「子ども食堂」「イベントスペース」「学習支援」などを組み合わせて運営する例も増えています。
要するに、収益よりも“やりがい”や“社会貢献”が原動力になっているのです。

ここで重要なのは、「副業だからこそ続く」という逆説です。
専業なら採算が合わずに潰れてしまいますが、趣味や副業であれば多少の赤字でも継続が可能です。
駄菓子屋は“利益”より“存在”そのものに価値があるのです。
駄菓子屋が潰れない本当の理由

こうして見てみると、駄菓子屋が潰れないのは奇跡でも偶然でもありません。

子どもにとっては100円で買える冒険、大人にとっては懐かしさを呼び起こすタイムカプセル。
地域にとっては交流のハブであり、運営者にとっては副業や趣味の舞台。
利益率が低くても、文化やコミュニティ、仕組みがそれを支えているのです。

つまり駄菓子屋は「商売」と「文化」と「居場所」が絶妙に混ざり合った存在です。市場原理だけでは測れない、半分はビジネス、半分はライフワーク。
だからこそ、街角に今もひっそりと明かりを灯し続けているのです。
最後に

コンビニの明かりが24時間消えない時代に、駄菓子屋のシャッターは時に気まぐれに閉まることがあります。

でも、ふと開いたとき、子どもたちの笑い声が響き、昔の記憶がよみがえります。
そんな場所が完全に消えてしまうのは、あまりにも惜しいことです。
駄菓子屋は、私たちが「効率」や「利益」では測れない価値をまだ大切にしている証拠なのかもしれません。

あなたの街にも小さな奇跡のように残っていませんか?
たまには100円玉を握りしめて、久しぶりにその扉を開けてみるのも悪くないと思います。