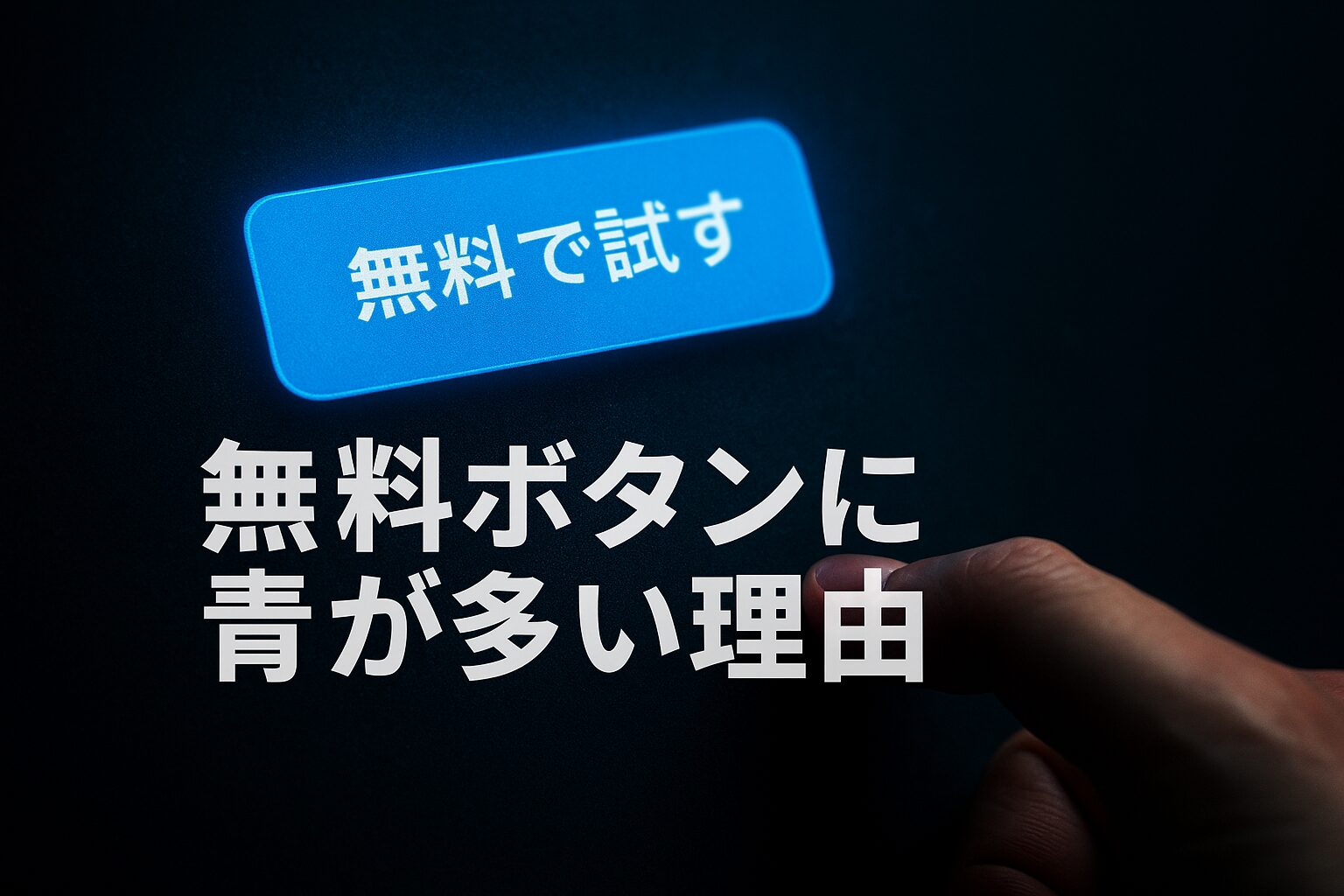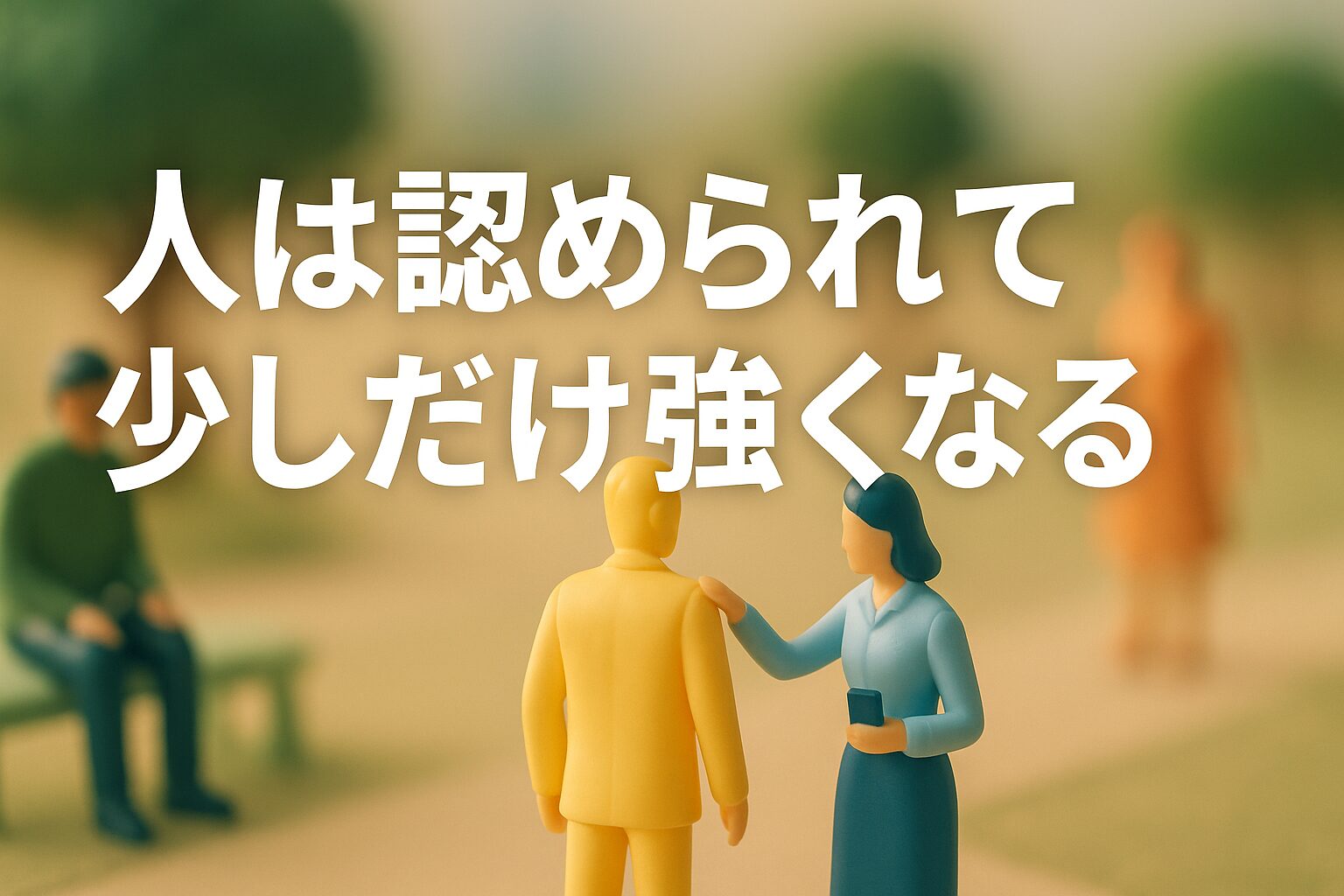焼き鳥屋はなぜ潰れないのか?4つの秘密

はじめに

街を歩けば必ず一軒は見つかる焼き鳥屋。


小さなカウンター席に漂う炭火の香り、赤提灯のほのかな明かり……。
不思議なことに、どの町でも健在で、しかも意外と長続きしています。


コンビニが閉店することはあっても、焼き鳥屋はしぶとく生き残る
――その秘密を探ってみましょう。
※本記事はエンターテインメント目的で制作されています。

1. ドリンクで稼ぐ「裏の本丸」

焼き鳥屋の真の利益源、それはズバリ「ドリンク」です。

居酒屋業界では、ドリンクの原価率は20〜30%が目安とされ、粗利率にすると70〜80%にも達します。
例えばハイボールやビールが1杯600〜1,500円。
実際の原価はその3割以下ですから、グラスを注ぐたびに利益が積み重なっていくのです。


焼き鳥は「客寄せパンダ」とも言える存在です。
香ばしい匂いに誘われて来店したお客さんは、気づけば2杯、3杯と杯を重ねています。
結果として会計の大部分はドリンクが占めることに。
お酒好きの心理を見事に突いた、飲食ビジネスの王道モデルなのです。
2. 仕込み技術が生む「高歩留まり」

焼き鳥の強みは、鶏を余すところなく使える点にあります。

もも、ねぎま、皮、レバー、ハツ、なんこつ……。
一羽の鶏から実に多彩な部位を串に仕立てられるため、廃棄が少なく、在庫ロスも出にくいのです。

さらに「串打ち3年、焼き一生」と言われるほど、仕込みには職人技が欠かせません。肉の大きさを持ち手から先端へと変化させて刺すなど、見た目と食感のバランスを計算した緻密な作業が求められます。
その技術こそが、高い粗利率(80%近い場合も!)を支えているのです。
つまり「焼き鳥屋は仕込みで決まる」
厨房で黙々と仕込まれる一本一本が、経営の安定を裏から支えているのです。
3. 常連コミュニティという「無形資産」

焼き鳥屋のカウンターに腰掛けると、見知らぬ隣の人と自然に会話が始まることがあります。
実はこれが経営にとって大きな強みです。
居酒屋業態はリピート率と口コミへの依存度が高く、常連客が多いほど経営は安定します。

「今日はレバー塩? いつものやつね」と大将が声をかけてくれれば、それだけで常連は嬉しくなります。
人は“自分を覚えていてくれる”ことに弱いのです。
SNSの「いいね!」に似ていて、承認欲求が満たされるからでしょう。
さらに常連は友人を連れて来てくれるので、新規顧客を自然に増やすことができます。

つまり焼き鳥屋は単なる飲食店ではなく、町の小さなコミュニティ。
赤提灯は看板であると同時に、「常連の絆」を照らすシンボルなのです。
4. 持ち帰り需要という「第二の戦場」

近年見逃せないのが、テイクアウトやデリバリー需要です。

Uber Eatsや出前館などが浸透し、焼き鳥はその中でも人気商品。
冷めても味が落ちにくく、弁当や丼への展開もしやすいのが強みです。
実際、日本のフードデリバリー市場は2024年に約226億ドル規模。
2030年には3,000億ドルを超えると予測されています。
外食全体も回復傾向にあり、夜は店内、昼は持ち帰りという「二毛作モデル」がますます現実味を帯びています。

小さな8席の店舗でも、持ち帰り窓口を作るだけで客数は倍増。
焼き鳥屋にとって、まさに「外部エンジン」と呼べる成長の柱なのです。
最後に

焼き鳥屋は“したたか”に生き残る
焼き鳥屋が潰れにくい理由を整理すると――
- 焼き鳥は香りで客を呼び、ドリンクで利益を稼ぐ
- 仕込み技術でロスを抑え、高歩留まりを実現
- 常連コミュニティが安定収益を生む
- 持ち帰り需要で売上の第二の柱を築く
つまり焼き鳥屋は見た目以上に「したたか」なのです。

一本の串には職人の技術と経営の知恵が詰まっています。
赤提灯の下に立ちのぼる煙は、単なる炭火の煙ではなく、小さな店が社会を生き抜く知恵の象徴なのかもしれません。

次に焼き鳥を頬張るときは、その裏にある“したたかな経営戦略”を思い出してみてください。
きっと一口が、これまで以上に味わい深く感じられるはずです。