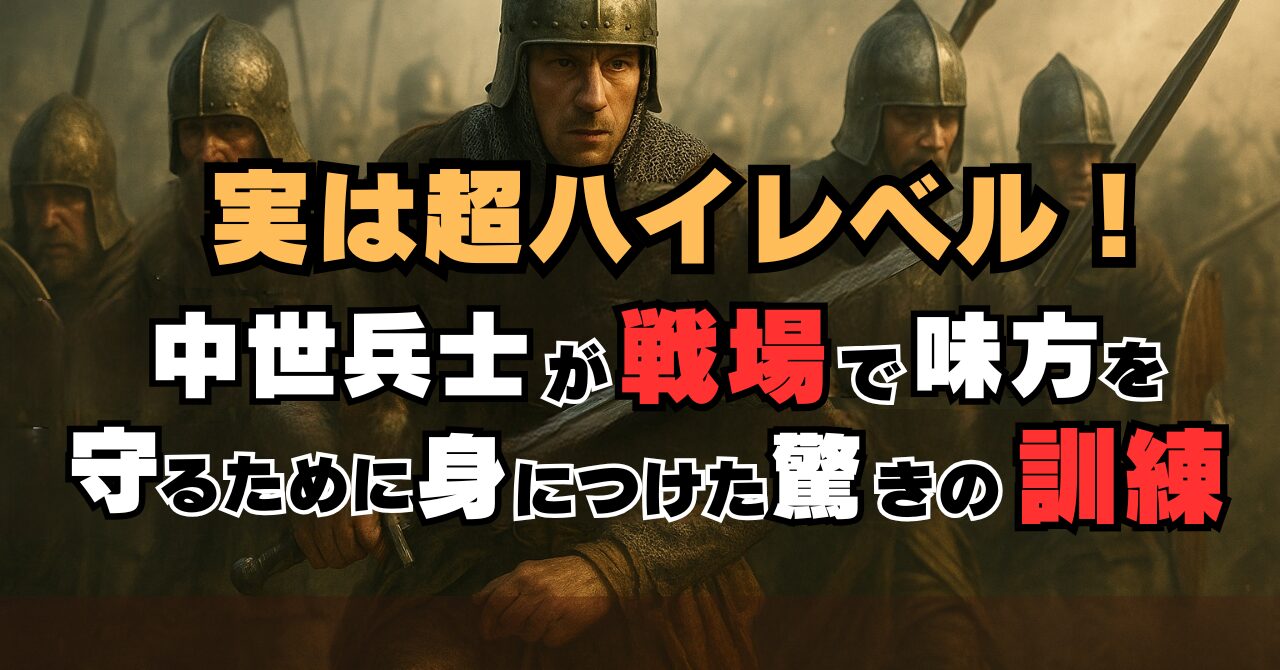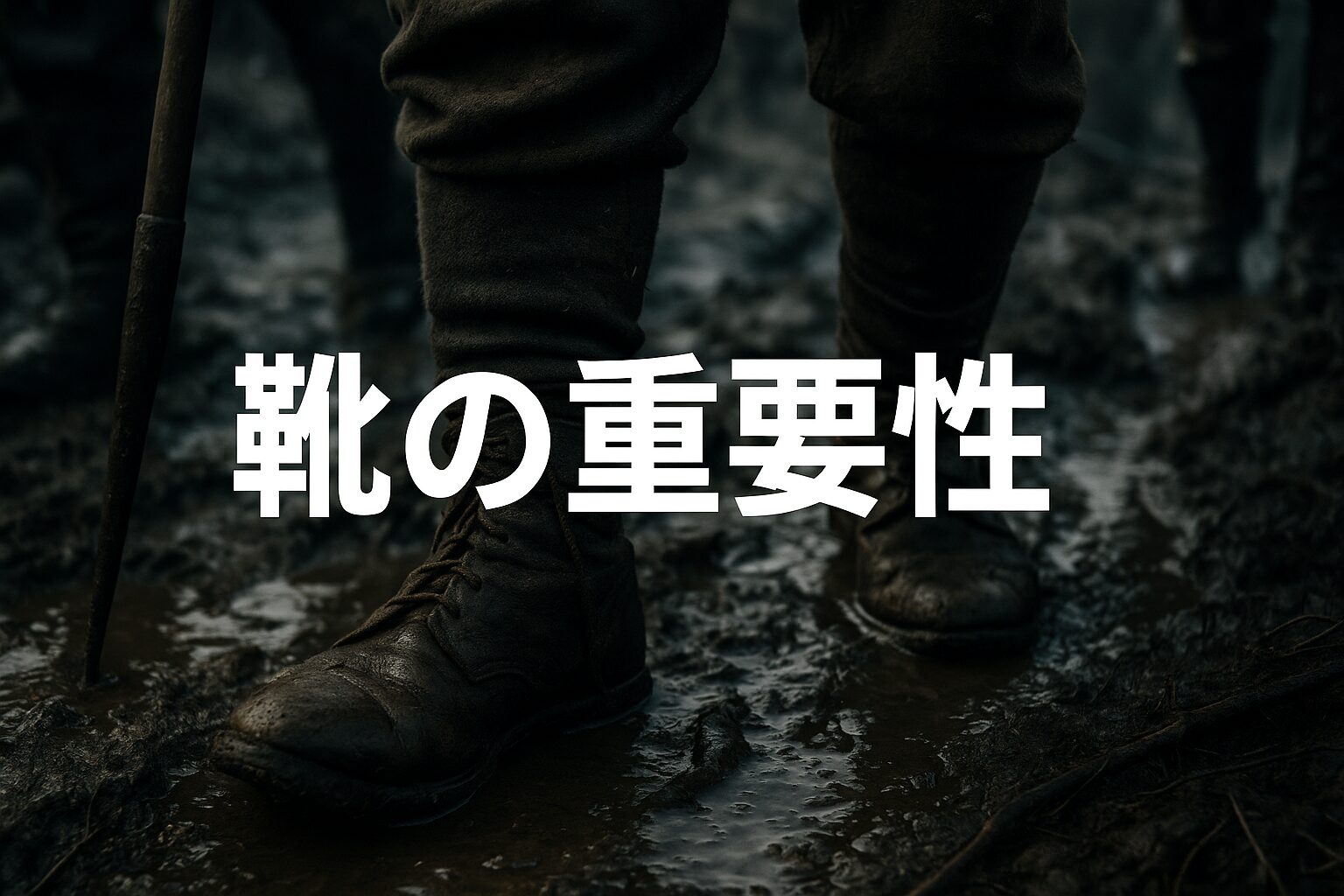なぜ“名もなき兵士”たちは命を懸けたのか?『王を守る影の軍勢──中世歩兵の誇りと報われぬ現実』


日給2ペンス。
食事は塩漬けの干し肉と硬いパンだけ。
捕まれば身代金なしで処刑、それでも彼らは前に進んだ。
はじめに

“地味すぎる英雄たち”の真実に迫る
中世ヨーロッパの戦場といえば、光り輝く鎧に身を包み、白馬に乗った騎士たち……といきたいところですが、現実はそんなにカッコよくありません。
実際に血まみれ・泥まみれで戦っていたのは、庶民の出である歩兵たち。
彼らの武器は借り物、食事は硬すぎるパン、報酬は雀の涙。
それでも彼らは戦いました。
なぜって?
「辞退します」
なんて言ったら、代わりに村ごと罰を受けるかもしれない時代です。
彼らは歴史の表舞台には立ちませんでした。
が、その土台はすべて彼らの肩にのしかかっていたのです。
いわば“縁の下の支柱”でした。
この記事では、そんな名もなき歩兵たちの知られざる現実を、5つの角度からズバッと掘り下げていきます。
騎士の影で踏まれながら、それでも踏ん張った彼らの物語、ちょっとのぞいてみませんか?
※本記事はエンターテインメント目的で制作されています。
🍞1. 食事という名の“忍耐トレーニング”

噛むだけで歯が折れる、メシが拷問。
歩兵たちの食事事情をひとことで言うなら、サバイバルというより“我慢大会”に近いものでした。
- 歯を試されるほど硬いライ麦パンや乾パン
- 塩だけで味つけされた干し肉(固い・しょっぱい・脂が少ない)
- チーズや乾燥豆は“ご褒美レベル”の希少食材
- 雑穀の粥は、水でのばされ、冷えた状態で支給されることも
「革靴を煮て食べた」──当時の兵士にとっては、冗談ではなく真実。
火を起こす燃料も限られ、寒さに震えながら冷えきった粥をすする毎日。
パンは文字どおり石のように硬く、食べるというより「砕く」作業に近かったようです。
栄養バランス?
カロリー設計?
そんな概念があるはずもなく、目的はただ一つ──
“今日を乗り切るための最低限”。
食事は戦う力を与えるものではなく、飢えによる死を先延ばしにするための手段だったのです。
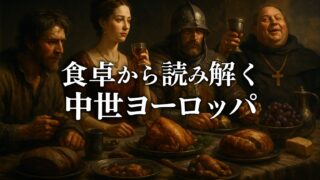
💰2. 報酬は騎士の12分の1

“命が安すぎる”歩兵の現実
戦場では、誰が矢に当たるかに階級は関係ありません。
でも、報酬となると話は別でした。
- 騎士:日給24ペンス(馬つき、身代金つき)
- 歩兵:日給2ペンス(飯つきでもなく、命も安い)
- 弓兵:日給3〜4ペンス(的にされる確率高め)
「命の値段は、身分で決まる」
歩兵は、自分の武器も防具も基本“自腹”。
宿泊場所も自力で確保。
つまり2ペンスの給料は、その日の食費と泥だらけの寝床代でほぼ消える計算です。
さらにひどいのは、給料の支払いタイミング。
多くの軍では戦後にまとめて渡す“後払い制”が一般的で、
- 戦争が終わらない → ずっと未払い
- 帰還できない → そもそも受け取れない
- 雇用主が逃げる → 給与消滅
……という“3コンボ”が普通にありました。
歩兵にとっての戦争は、給料目当ての仕事というより、“当たれば大損、勝っても損”という割に合わないギャンブルだったのです。
🏕️3. 寝床は泥、まくらは恐怖

歩兵たちのリアル戦場ライフ
「地獄のような生活」とは、こういうものを言います。
- 雨が降ろうが風が吹こうが、地面に直寝(マットレス? そんな贅沢ありません)
- 寒さ対策は藁か獣の皮。凍えたまま朝を迎える兵も多かった
- ノミ・シラミは“常駐住民”。かゆみで眠れず、皮膚病も蔓延
- ケガをしても放置。膿が広がって死ぬか、生き延びるかは“運次第”
- 夜襲を警戒し、武器は手放さずに就寝(つまり熟睡できない)
「眠る=無防備。だから寝るのも命がけ」
水? 手に入ればラッキー。
入浴はもちろん、顔を洗うだけでも貴族のような行為。
兵士たちは、常に悪臭・汚れ・感染症にさらされながら任務をこなしていました。
それでも、村に家族を残して戦場に立った彼らは、
「生きて帰れた者=選ばれし者」
という、悲しすぎる現実を当然のように受け入れていたのです。
🔥4. 「戦いたい」じゃない「戦うしかなかった」

歩兵たちの選べない理由
ここまで過酷な待遇、理不尽な環境──それでも歩兵たちは前に出ました。
なぜか?
強い意志や高い志があった?
そんなキレイな話ではありません。
彼らが“戦わされた”7つの現実
- 王や領主への絶対的な忠誠(断れば裏切り者)
- 仲間との絆(“置いて逃げられない”連帯感)
- 戦利品や略奪による“運試し的収入”への期待
- 戦功を立てれば土地・名誉が手に入るという噂
- 軽犯罪者なら兵役で“罪をチャラに”できる特典つき
- 働き口ゼロの社会で、兵士だけが“現実的な選択肢”
- 敗北=死、というシンプルすぎるルール
「理想なんてない。ただ、他に道がないだけだった」
しかも、騎士と歩兵の扱いには天と地ほどの差がありました。
- 騎士 → 捕虜になれば交渉の余地あり。身代金で帰還も可能
- 歩兵 → 捕虜になれば即処刑か奴隷。交渉の余地ゼロ
誰にも覚えられないまま、戦場に消えていく──
それでも彼らは任務を遂行しました。
仲間とともに、命令に従って、最後まで。
それは「忠誠」ではなく、逃げ場のない「現実」だったのです。
🛡️5. 実は“勝敗を分ける本命”だった歩兵たち

戦局を動かしたのは、名もなき足音だった。
「歩兵=数合わせ」
──そう思ったら大間違い。
中世後期、歩兵はただの“補助要員”ではなく、戦術の主軸に躍り出ていたのです。
✅ 実際の現場での“歩兵の仕事”一覧
- 騎兵の突撃を止める長槍の密集陣形(見た目以上に怖い)
- 弓やクロスボウによる遠距離の火力支援(重装備騎士でも貫通)
- 攻城戦での梯子かけ・壁破壊・トンネル掘削(命がけの地味作業)
- 補給線の確保、野営地づくり、周囲の警備・偵察(全体の基盤)
「戦場で“動く人力インフラ”といえば彼ら」
13世紀以降、彼らなしでは成り立たない戦術が生まれました。
象徴的なのは「金拍車の戦い」(1302年)
フランドルの歩兵たちは、鉄の訓練と組織力で圧倒的な騎士軍団に挑みました。
戦場は沼地と水路が多く、騎兵にとっては不利な地形。
そこに誘い込まれたフランス騎士団は、突撃力を活かせず混乱。
フランドル歩兵たちは密集した長槍陣形を築き、重装の騎士たちを次々に足止めし、打ち倒しました。
この戦いは「歩兵が騎士を制する」初めての明確な実例とされ、戦術思想そのものを揺るがす一撃でした。
装飾を脱ぎ捨て、盾と槍で武装した無名の市民兵が、“無敵”とされてきた騎士団に歴史的な敗北を突きつけたのです。
歩兵はただの“安価な盾”ではなく、
「現場を支え、勝敗を決する“真の主役”」
になっていったのです。
🏁 最後に

歴史を支えた“名もなき前線”の英雄たち
歩兵たちは、決して勲章や拍手を求めて戦っていたわけではありません。
- 仲間の命を守るため
- 明日の朝を迎えるため
- ほんの少しでも、自分の人生がマシになることを願って
彼らは最前線で戦い、泥に倒れ、名前も残らず消えていきました。
それでも。
その一歩一歩が道となり、その命の重なりが国の形をつくっていたのです。
「英雄とは、名を知られた者ではなく、無名のまま支え続けた者たちのことかもしれません」
歴史は、勝者や偉人たちだけのものではありません。
今こそ──
その影で支え続けた“歩兵たちの物語”に、敬意を払うときではないでしょうか。
📝 もしこの記事が、あなたの心に少しでも何かを残したなら──
「こんな歴史があったこと」を広めるために、ぜひシェアをお願いします。
📌 #中世史 #知られざる兵士たち #歴史は足元から動いた
4コマ漫画「戦功の褒美」